
車を運転していると突然の故障に見舞われることがあります。そんな時に頼りになるのが故障車の牽引です。しかし、適切な手順を踏まずに牽引を行うと、車両の損傷や事故の原因となってしまいます。
この記事では、故障車の牽引に関する正しい手順と注意点について詳しく解説します。自分で牽引を行う場合の具体的な方法から、業者への依頼方法まで、実際の現場で役立つ情報をお伝えします。
故障車牽引時における基本知識

故障車の牽引は、動かなくなった車両を他の車両で引っ張って移動させる方法です。緊急時に非常に有効な手段ですが、道路交通法に基づいた厳格なルールが存在します。
牽引が必要なケース
牽引には大きく分けて2つの方法があります。ロープやワイヤーを使用する「牽引」と、レッカー車などの専用車両を使用する「搬送」です。一般のドライバーが行えるのは前者の牽引のみで、後者は専門業者による作業となります。
牽引が必要となる代表的な故障例は、エンジンの始動不良やオーバーヒート、バッテリー上がりなどが挙げられます。以下では、牽引が必要となる代表的な故障例について、故障の種類ごとに症状や牽引の必要性を表にまとめました。これを参考に、各故障の発生時にどの程度の対応が求められるかを確認してください。
| 故障の種類 | 症状 | 牽引の必要性 |
|---|---|---|
| エンジン始動不良 | エンジンがかからない | 高い |
| オーバーヒート | エンジンが過熱して停止 | 中程度 |
| バッテリー上がり | 電気系統が作動しない | 低い(ジャンプスタート可能) |
| タイヤのパンク | 走行が困難 | 低い(スペアタイヤ交換可能) |
| ブレーキ故障 | 制動力が効かない | 非常に高い |
牽引可能な車両と制限
すべての車両が牽引可能というわけではありません。道路交通法では、牽引される車両の重量が750kg以下であれば、牽引免許は不要です。しかし、750kgを超える車両を牽引する場合でも、故障車や自走不可能となった車をロープまたはクレーンで牽引する際には、牽引免許は必要ありません。
牽引する際は、それぞれの車の間が5m以内になるように道路交通法で定められています。この制限は、牽引車と被牽引車の間で急激な引っ張りや急停止が発生しないようにするためです。距離が短すぎると、車両同士が追突する危険が高まり、逆に距離が長過ぎると、車両の操作が難しくなり、連携が取れなくなる可能性があります。
そのため、牽引ロープの長さも重要です。牽引ロープの長さは、一般的に3〜5mの範囲で使用することが推奨されています。この長さであれば、車両の間隔を適切に保ちながら、安全に牽引作業を行うことができます。ロープが短すぎると車両間に必要な余裕が取れず、長過ぎると牽引時の安定性が低下するため、最適な長さを選ぶことが大切です。
故障車牽引の準備と必要な道具
安全な牽引を行うためには、事前の準備が欠かせません。必要な道具を揃え、正しい手順で準備を進めることが重要です。
必要な道具と装備
牽引に必要な基本的な道具は以下のとおりです。これらの道具は車載工具と併せて常備しておくことをお勧めします。
- 牽引ロープ(自動車用の強度が十分なもの)
- 白い布または反射テープ
- 三角表示板(停止表示器材)
- 軍手またはゴム手袋
- 懐中電灯(夜間作業時)
- 緊急連絡先のメモ
牽引ロープの選び方
牽引ロープは車両の重量に対して十分な強度を持つものを選ぶ必要があります。一般的な家庭用ロープでは強度不足で、牽引中に切れてしまう危険性があります。
自動車用の牽引ロープは、通常2tから5tの荷重に耐えられる設計になっています。購入時は必ず自動車用として販売されているものを選び、パッケージに記載された最大荷重を確認してください。選び方を間違えると、事故の際にロープが切れてしまい、大きな危険を伴います。
また、牽引ロープは素材にも注意が必要です。ナイロン製のロープは耐久性が高く、伸縮性もあるため、衝撃を吸収する特性があります。鋼鉄製のワイヤーロープも強力ですが、取り扱いには注意が必要です。ロープの素材や特徴を考慮し、最適なものを選びましょう。
牽引フックの確認方法
牽引を行う前に、両方の車両に牽引フックが装備されているか確認する必要があります。多くの車両では、フロントバンパーやリアバンパーの下部に設置されています。
一部の車両では、牽引フックが収納式になっており、必要時に取り出して装着するタイプもあります。事前に取扱説明書で確認し、フックの位置と取り付け方法を把握しておきましょう。牽引フックの取り付け方を誤ると、作業中にフックが外れてしまうことがあります。
また、牽引フックには「牽引用」と「牽引不可」の表示がされている場合もあります。間違った部品を使うと、牽引中にフックが外れ、車両に損傷を与えたり、事故が発生したりする恐れがあるため、フックの確認は必須です。フックがしっかりと装着されているかを目視で確認し、必要に応じて点検も行いましょう。
牽引手順の詳細解説

実際の牽引手順は複数のステップから成り立っています。各ステップを正しく実行することで、安全な牽引が可能になります。
作業前の安全確認
牽引作業を開始する前に、周囲の安全を確保することが最優先です。交通量の多い道路では、可能な限り安全な場所に車両を移動させてから作業を開始しましょう。
三角表示板を故障車の後方50m以上離れた場所に設置し、他の車両に故障車の存在を知らせます。夜間や視界の悪い状況では、ハザードランプを点灯させて注意を促すことも重要です。
牽引ロープの取り付け
牽引ロープの取り付けは、正しい手順で行う必要があります。まず、牽引車と被牽引車の牽引フックを確認し、ロープを適切に固定します。
ロープを取り付ける際は、結び目が緩まないよう確実に固定してください。また、ロープの中央部分には義務付けられている白い布を取り付けます。これは他のドライバーに牽引中であることを知らせる重要な安全対策です。白い布は、目立つ色のものを使用することで、さらに安全性を高めることができます。
牽引ロープを取り付ける前に、周囲に十分な注意を払い、他の車両や歩行者がいないかを確認します。また、牽引ロープが伸びすぎたり、引っ張られ過ぎないように、適切な長さで取り付けることも重要です。ロープの長さが適切でないと、牽引中に急激な負荷がかかり、事故の原因となることがあります。
車両の準備と設定
被牽引車では、サイドブレーキの解除とギアポジションの調整を行います。オートマチック車の場合はNレンジ(ニュートラル)に、マニュアル車の場合はニュートラルに設定します。
エンジンがかかる場合には、パワーステアリングやブレーキブースターの効きを確保するため、エンジンをかけた状態で牽引を行います。エンジンが動いていることで、ハンドル操作がスムーズになり、ブレーキの効きが保たれます。特に重い車両や急勾配を牽引する際は、エンジンの力が非常に重要です。
エンジンがかからない場合は、ハンドル操作とブレーキ操作により多くの力が必要になることを理解しておきましょう。手動で操作する場合、特にブレーキが効きにくくなるため、注意深く行動することが求められます。また、牽引前に車両の各部位に問題がないかを事前にチェックしておきましょう。
牽引中の運転技術と注意点

牽引中の運転は通常の運転とは大きく異なります。特別な技術と注意が必要で、両方の車両の運転者が連携して安全に走行しなければなりません。
発進時の注意点
牽引での発進は、通常よりもゆっくりと行う必要があります。急発進はロープに急激な負荷をかけ、切断や車両の損傷の原因となります。
牽引車の運転者は、被牽引車の準備が整ったことを確認してから発進してください。発進時はロープが徐々に張るよう、アクセルを非常にゆっくりと踏み込みましょう。これにより、牽引車と被牽引車がスムーズに連動し、過度な衝撃を避けることができます。
また、牽引車が発進する際、周囲の交通にも注意を払い、他の車両と十分な距離を保つことが大切です。特に信号の変わるタイミングや車両の流れに注意し、急な動きがないようにすることで、牽引作業がより安全に行えます。
走行中の速度管理
牽引中の速度について、一般道路では自動車の法定速度は時速60kmですが、牽引ロープを使用した牽引の場合、速度は時速40km以下に抑えるべきです。速度を超えると、牽引中に車両が不安定になり、事故のリスクが高くなりますので、十分に注意しましょう。
また、高速道路では最低速度が時速50kmと定められており、牽引ロープを使用した走行は危険なため原則として禁止されています。牽引が必要な場合は、自力での対応は避け、専門の業者による牽引サービスを依頼しましょう。
カーブと坂道での走行
カーブでの走行では、牽引ロープの長さを考慮して大回りする必要があります。被牽引車は牽引車よりも内側を通るため、十分な余裕をもってカーブを描きましょう。
上り坂では牽引車に大きな負荷がかかるため、エンジンの過負荷に注意が必要です。下り坂では被牽引車の重量により牽引車が押される形になるため、エンジンブレーキを活用した慎重な運転が求められます。また、エンジンが過負荷にならないよう、事前に車両の状況を確認しておきましょう。
下り坂では、被牽引車の重量により牽引車が押される形になるため、エンジンブレーキを活用した慎重な運転が求められます。下り坂では速度が自然に増加するため、ブレーキをかけるタイミングが重要です。急な下り坂では、事前にブレーキを軽くかけて速度を調整し、安全に走行しましょう。
車種別の牽引可否と注意点
すべての車両が牽引可能というわけではありません。車種や駆動方式により、牽引方法に制限がある場合や、牽引自体が禁止されている場合があります。
四輪駆動車の注意点
四輪駆動車(4WD)の牽引には特別な注意が必要です。4WDシステムが作動している状態で牽引を行うと、駆動系統に深刻な損傷を与える可能性があります。
多くの4WD車では、牽引時に2WDモードに切り替えるか、すべての車輪を地面から離した状態での搬送が推奨されています。取扱説明書で牽引方法を必ず確認してから作業を行ってください。4WD車の多くは、牽引中に4WDシステムをオフにすることで、駆動系統の損傷を防ぐことができます。
また、牽引前に牽引フックの取り付け位置を必ず確認してください。4WD車では、車両によって牽引フックの設置位置が異なることがあり、正しい位置にフックを取り付けることが、牽引中の安全性を高めます。適切な準備を整えた上で作業を行うことが、トラブルの防止につながります。
電気自動車とハイブリッド車
電気自動車やハイブリッド車の牽引には、特別な配慮が必要です。これらの車両では、牽引により発電機が回転し、高電圧が発生する危険性があります。
多くの電気自動車メーカーでは、安全上の理由から牽引を禁止しています。故障時は必ず専門業者による搬送を依頼し、自力での牽引は避けてください。牽引を行う場合、専用の車両や装備を用意する必要があるため、一般的な牽引方法は適用できません。
電気自動車やハイブリッド車の牽引時には、牽引車のエンジンがかかっている状態での牽引を避けることが推奨されます。これにより、車両のバッテリーやシステムへの過剰な負担を避け、最適な安全性を確保することができます。専門業者に依頼することで、リスクを最小限に抑えることが可能です。
輸入車の特殊事情
輸入車の中には、日本の道路事情に合わせた牽引フックが装備されていない場合があります。また、車両の構造上、牽引が推奨されていない場合もあります。
輸入車を牽引する場合は、正規ディーラーや専門業者に事前に相談し、適切な牽引方法を確認することが大切です。無理な牽引は高額な修理費用につながる可能性があります。特に、車両構造に適した牽引方法を確認せずに作業を進めると、車両に深刻なダメージを与えてしまうことがあります。
また、輸入車の中には牽引に対応していない車両や、特殊な条件下でのみ牽引が許可されている車両もあります。これらの車両を牽引する際は、事前に取り扱い説明書を確認し、適切な指示に従うようにしましょう。専門的な知識を持った業者に依頼することが、安全な牽引に繋がります。
自動車保険付帯サービスの活用

多くの自動車保険には、ロードサービスが付帯されています。これらのサービスを活用することで、故障時の負担を軽減できます。
保険会社のロードサービス
保険付帯のロードサービスは、多くの場合、年間利用回数に制限があります。また、牽引距離にも制限があるため、契約内容を事前に確認しておくことが重要です。契約時に無料で提供される距離を超えた場合、追加料金が発生することがあるため、注意が必要です。
ロードサービスを利用する際は、事前にサービス内容や条件をよく理解し、適切に利用することが大切です。緊急時には迅速に対応してもらえる一方、条件を満たしていない場合はサービスが受けられないこともあるため、利用規約の確認を怠らないようにしましょう。
サービス内容の確認方法
保険証券や約款に記載されているロードサービスの内容を確認してください。無料牽引距離、年間利用回数、対象となる故障内容などが詳しく記載されています。
不明な点がある場合は、保険会社のカスタマーサービスに問い合わせ、具体的なサービス内容を確認しましょう。緊急時に慌てないよう、平常時に確認しておくことが大切です。特に、利用条件や制限について理解しておくことで、実際にサービスを利用する際に問題を避けることができます。
また、契約内容によっては、特定の修理業者に依頼する必要がある場合や、指定された業者の利用が義務付けられていることもあります。これらの条件も事前に確認しておくことで、無駄なトラブルを防ぐことができます。
利用時の注意点
保険付帯のロードサービスを利用する際は、契約者本人が運転している場合に限定されることがあります。また、保険契約車両以外での故障には対応していない場合もあります。
利用回数が制限を超えた場合や、無料牽引距離を超えた場合は、追加料金が発生します。これらの制限を把握し、必要に応じて他のサービスとの併用を検討してください。例えば、無料で提供される回数や距離を超えた場合、次回の利用時に追加料金がかかることを事前に把握しておくことが重要です。
ロードサービスを利用する際は、料金が追加される場合やサービス範囲が制限されることがあるため、可能であれば事前にサービス内容や制限事項について確認しておくと便利です。そうすることで、緊急時でもスムーズに対応できるようになります。
故障時の安全対策と連絡手順
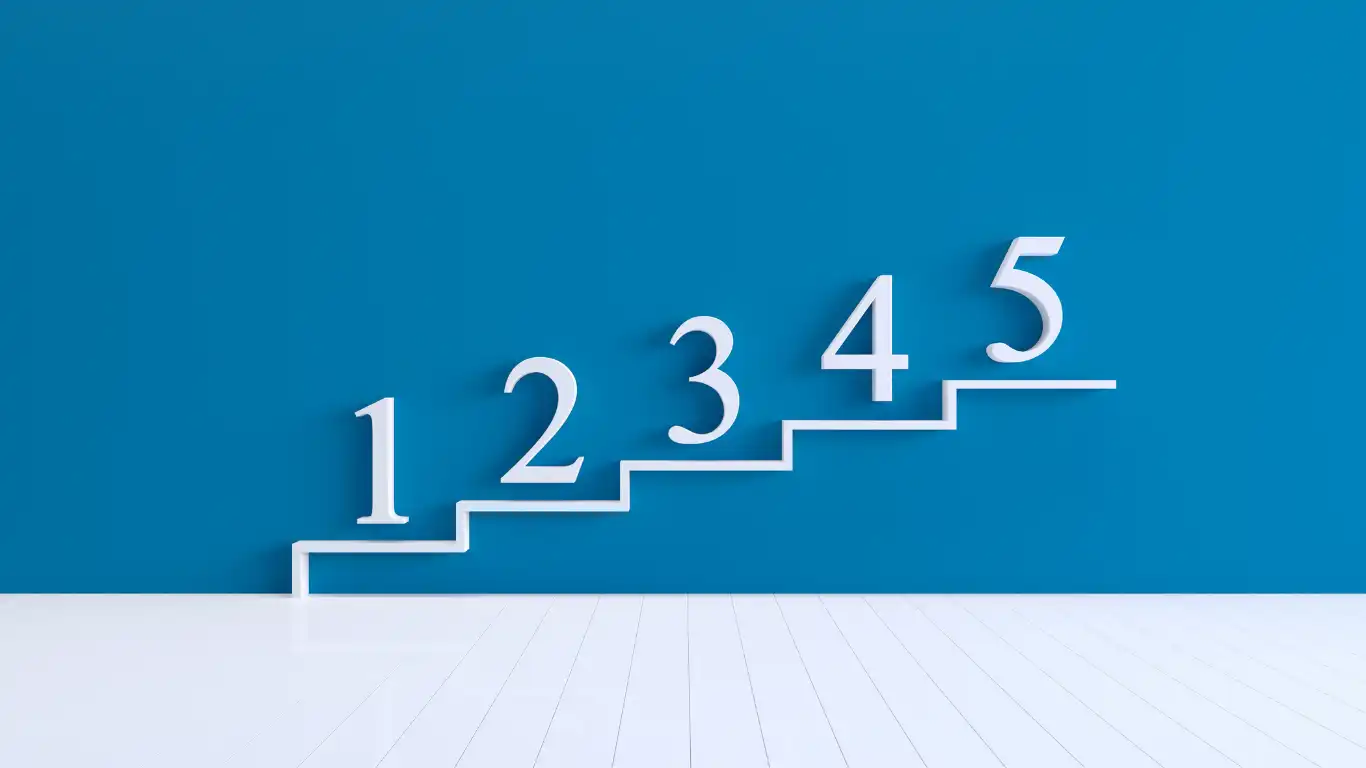
車が故障した際は、適切な安全対策を行うことが何よりも重要です。二次災害を防ぎ、安全に救援を待つための手順を理解しておきましょう。
緊急時の初期対応
故障を感じたら、まず安全な場所に車を停止させます。可能な限り路肩や駐車場など、交通の妨げにならない場所を選んでください。
車を停止したら、ハザードランプを点灯させ、エンジンを停止します。その後、三角表示板を車両後方に設置し、他の車両に故障車の存在を知らせます。
さらに、故障の種類によっては、車内にとどまらず、車外に避難する必要があります。特に交通量が多い道路や高速道路では、事故のリスクを避けるために、車両から離れ、安全な場所に移動することが重要です。
連絡先の優先順位
故障時の連絡先は、状況に応じて以下の優先順位で選択してください。まず、負傷者がいる場合は119番通報を最優先とします。
負傷者がいない場合は、加入している自動車保険のロードサービス、道路緊急ダイヤルの順で連絡を検討します。連絡先と利用条件を事前に確認し、緊急時に迷わないよう準備しておきましょう。保険のロードサービスは、通常の事故や故障の対応をカバーしているため、加入内容を事前に把握しておくと安心です。
また、もし自動車保険のロードサービスが利用できない場合は、専門業者やサービスを利用する選択肢も考慮する必要があります。救援サービスの手配ができた場合でも、作業内容や到着までの時間を確認し、何が必要なのかを事前に伝えておくことが、スムーズな対応に繋がります。
安心して依頼できる方法
安心してロードサービスを依頼するためには、まず信頼できる業者やサービスを選ぶことが重要です。事前に、ロードサービス会社や保険の提供するサービス内容、対応速度や評判を調べておくと、トラブル時にスムーズに対応できます。
また、緊急時に備えて、利用するサービスの電話番号や連絡先を車内に常備し、予めサービス内容を確認しておくことが有効です。特に、保険のロードサービスを利用する際は、契約内容や制限を事前に把握しておき、利用条件に合ったサービスを選ぶようにしましょう。
故障車牽引の費用と相場

故障車の牽引にかかる費用は、依頼する業者や距離、時間帯によって大きく異なります。事前に費用の相場を知っておくことで、適切な判断ができます。
業者別の料金比較
自動車クラブの会員の場合、基本的な牽引サービスは無料で受けられますが、非会員の場合は13,000円程度の基本料金がかかります。民間のロードサービス会社では、更に安価なサービスを提供している場合もあります。
保険付帯のロードサービスでは、契約内容にもよりますが、年間1〜2回程度の無料サービスが受けられることが一般的です。利用回数制限を確認し、計画的に利用することが重要です。契約内容によっては、牽引サービスに回数制限が設けられていることもあるため、利用前に詳細な情報を把握しておきましょう。
業者ごとにサービス内容や料金が異なるため、料金だけでなく、対応スピードや提供されるサポート内容(例えば、24時間対応や緊急時の迅速な出動など)を総合的に判断することも大切です。サービスの質や評判も確認し、コストパフォーマンスを考慮した選択が求められます。
距離別の追加料金
無料牽引距離を超えた場合の追加料金は、1kmあたり数百円から1,000円程度が相場です。長距離の牽引が必要な場合は、事前に見積もりを取り、費用を確認してください。
夜間や休日の割増料金も考慮する必要があります。これらの時間帯では、基本料金の20〜50%程度の割増料金が発生することが一般的です。繁忙時間や緊急時の対応が求められるため、通常の営業時間外には料金が増加することを理解しておきましょう。
まとめ
故障車の牽引は、適切な知識と準備があれば安全に実行できる作業です。しかし、法的な制限や技術的な要件を理解し、無理をしない判断が重要です。
自力での牽引を行う場合は、必要な道具の準備、正しい手順の実行、法令遵守が不可欠です。特に、牽引ロープの取り付けや白い布の装着、速度制限の遵守など、基本的なルールを守ることが安全な牽引の前提となります。
普段から取扱説明書で牽引方法を確認し、必要な道具を車に常備しておくことで、緊急時に冷静に対応できるでしょう。故障は予期せぬタイミングで発生するため、事前の準備と正しい知識が最も重要な安全対策となります。

最短30分で駆けつけます!
車の故障・パンク・事故車のけん引など、
車のトラブルは「カーレスキュー隊24」に
お任せください。
便利なお支払い方法も充実!
-
現金OK

-
カード払いOK

-
後払い決済OK








