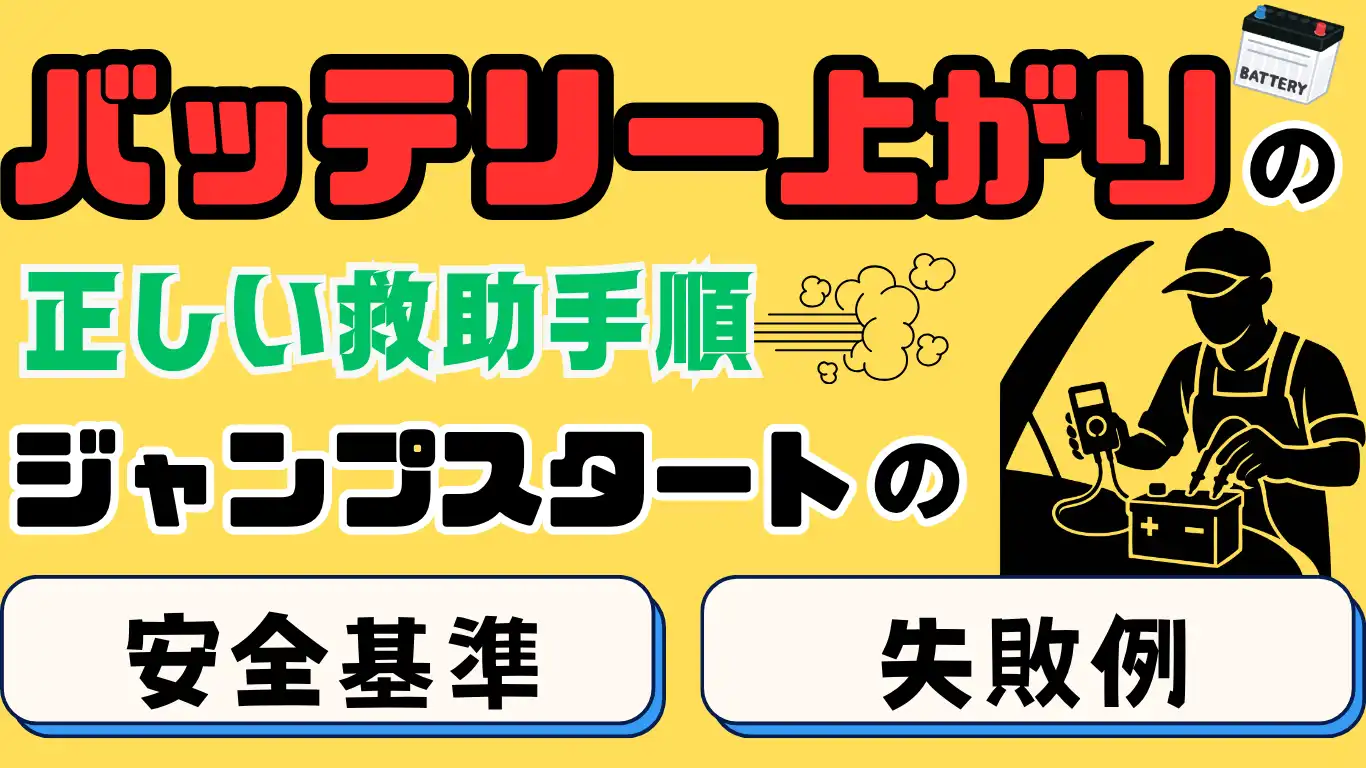
バッテリー上がり(過放電)の際、安全なジャンプスタートの手順とやり方を専門家が解説。
ブースターケーブルの繋ぎ方、+/−極性の確認、アースポイントの選び方、逆接続の危険、HV/EV車の注意点、ロードサービス料金まで、失敗しない救援方法を徹底解説します。
安全第一。極性と手順を守れば多くは復旧できる

バッテリー上がりの救援(ジャンプスタート)は、正しい手順と極性(プラス/マイナス)を厳守すれば、多くのケースで安全に復旧が可能です。
ブースターケーブルの接続順序を守ることは、電気系統へのダメージ(ECU故障など)や、バッテリーから発生するガスの引火爆発(逆接続)を防ぐために不可欠だからです。特に、故障車のマイナス端子(−)に直接ケーブルを繋ぐことは、火花による爆発を招く危険な行為とされています。
救援車から電力を供給する際、誤って上がった車のマイナス端子(−)に直接接続すると、火花が飛び、バッテリー付近にある水素ガスに引火する危険があります。このため、必ずエンジンブロックの金属部(アース=電気を逃がす金属部)に繋ぐという手順が、安全基準として定められています。
ひとことまとめ
ジャンプスタートの正しい手順と極性(+/−)の確認は、安全基準の基本中の基本です。不安な場合は無理せずロードサービスを呼びましょう。
バッテリー上がりの見分け方(症状)

バッテリー上がりの症状は、エンジンをかけようとしたときの音や、電装品の動作状態から簡単に判断できます。
バッテリーの電力が不足すると、最も多くの電流を必要とするスターターモーター(セルモーター)が正常に機能しなくなるためです。また、電力不足はライトやワイパーの動きにも影響を及ぼします。
- キーを回した時に「グウゥ」という重い音で、セルモーターの回りが悪い場合。
- キーをひねっても「カチカチ」という異音しかせず、エンジンがかからない場合(特に重度の過放電)。
- ヘッドライトの明るさが、エンジン回転数が低い状態では暗く、エンジン回転を上げると明るくなる場合(オルタネーター(発電機)の充電に頼っている状態を示唆)。
- 冬場は気温が低いためバッテリーの性能が低下しやすく、朝のエンジン始動時にトラブルが起きやすいです(例:マイナス20度でバッテリー能力は50%に減少)。
- ウインカー(フラッシャー)をつけた時に、ライトと一緒に明滅する(暗くなったり明るくなったりする)場合、バッテリーの劣化またはアース不良が考えられます。
ひとことまとめ
カチカチ音や、ライトが弱くなる(フッシャーの点滅も暗くなるなど)異変を感じたら、それはバッテリー上がり(過放電)のサインです。
準備と安全(Pレンジ・サイドブレーキ・保護具)
ジャンプスタート作業の開始前には、車両の安全を確保し、作業中のショートや爆発、感電などの事故を防ぐために、細心の注意を払って準備を行わなければなりません。
安全な作業環境を確保し、特にバッテリーから発生する水素ガスや強い酸性を持つバッテリー液(希硫酸)から作業者を守るためです。また、路上安全は二次災害を防ぐための法令上の義務でもあります。
具体的な準備と安全手順
-
車両の設置とエンジン停止
・救援車と故障車を、ブースターケーブルが届く距離で、互いのエンジンが向かい合わないように(通常は並行して)駐車させます。
・両車ともシフトレバーをPレンジ(パーキング)またはニュートラルに入れ、サイドブレーキをしっかり引きます。
・救援車のエンジンを必ず停止させます。 -
路上での安全対策(法令遵守)
・ハザードランプを点灯させ、後続車に異常を知らせます。
・高速道路上や危険な場所では、三角表示板または発炎筒(法令に基づき装備必須)を後方に設置します。
・雨天、水たまり、電線近くでの作業は感電やショート、スリップの危険があるため絶対に避けてください。 -
電装品のOFF
故障車・救援車ともに、ヘッドライト、エアコン、オーディオなどのアクセサリー類(電装品)はすべてOFFの状態にします。 -
保護具の着用
バッテリー液は希硫酸を含んでおり危険です。作業時には、保護メガネや手袋を着用し、目や皮膚を保護します。 -
取扱説明書の確認
特に最近の車両やアイドリングストップ車(AGM/EFB)、ハイブリッド車(HV)は、バッテリーの位置やアースポイントが指定されている場合があるため、取扱説明書を必ず確認し、各社サポートの指示を最優先します。
ひとことまとめ
安全な場所で、Pレンジ、サイドブレーキ、電装OFF、そして保護具の着用を徹底してから、作業を開始しましょう。
車種別の可否[表](ガソリン/ディーゼル/AGM・EFB/HV・EV)

車種やバッテリーの種類によって、ジャンプスタートの可否や必要なケーブルの仕様が異なります。特に大電流が必要なディーゼル車や、電気系統が複雑なHV/EV車は注意が必要です。
ディーゼル車は始動トルクが大きく、大電流を必要とします。また、最新のアイドリングストップ車やHV/EV車は、ECU(エンジン制御ユニット)が充電制御を担っているため、予期せぬ故障を防ぐための特別な手順が求められます。
車種別のジャンプスタート可否早見表
| 車種区分 | 救援可否 | 必要な注意点(プロ推奨レベル) |
|---|---|---|
| ガソリン車(通常バッテリー) | 相互に可能 | 正しい接続手順(特にアースポイント)と極性(+/−)厳守。 |
| ディーゼル車 | 救援車側:可能/故障車側:可能 | 太いブースターケーブルが必須。救援車は電圧・容量が大きいものが望ましい。 |
| AGM/EFB車(アイドリングストップ車) | 可能(通常車から救援可) | 車両指定の接続ポイント(多くはエンジンルーム内)を使用。バッテリー交換や脱着後はECU再学習が必要な場合がある。 |
| HV/EV車(ハイブリッド/電気自動車) | HV車から他車への救援は不可/12V補機バッテリーへの給電は可能 | 高電圧系統(HV系統)の部品(オレンジ色の配線など)に絶対に触れない。指定された12V補機バッテリー端子(またはジャンピングポイント)のみ使用。必ずプロに依頼推奨。 |
ひとことまとめ
高電圧を扱うHV/EV車への救援は、12Vの補機バッテリーへの給電のみが可能です。自己判断が難しい場合は、プロのロードサービスを利用しましょう。
ケーブル選び(太さ・長さ・材質・クリップ)

ブースターケーブルを選ぶ際は、電圧(12V車か24V車か)だけでなく、救援対象の車種(特に大電流を必要とする車)に対応できる太さ(許容電流)と、安全に作業するための長さを確保することが重要です。
細すぎるケーブルは、大電流が流れる際にケーブルが発熱し、性能が発揮できないばかりか、被覆が溶けてショートする危険があるからです。ディーゼル車は特に大きな電流が必要なため、太いケーブルが必須となります。
ブースターケーブル仕様早見表
| 項目 | 選び方の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 電圧 | 12V車用か24V車用かを確認。 | 異なる電圧の車同士を繋ぐのは危険な逆接続です。 |
| 太さ(許容電流) | ガソリン車:細めでも対応可能。ディーゼル車:太いものを選ぶ。 | 細いケーブルで無理に始動させると、ケーブルが発熱・溶解する危険があります。 |
| 長さ | 3.5m〜5.0mが推奨 | 長すぎると電圧が低下し、短すぎると安全な駐車位置(ボンネットを向かい合わせにしない)が取れません。 |
| 色分け | 赤がプラス(+)、黒がマイナス(−)であることを確認。 | 極性を間違えないための、最も重要な目印です。 |
| 材質/クリップ | 銅線が太く、クリップが端子をしっかり挟める強度があるもの。 |
ブースターケーブルの繋ぎ方以前に、ケーブル選びが安全基準の第一歩です。ディーゼル車(特に24V車)の救援には、必ず十分な太さを持つケーブルを用意しましょう。
接続手順(車同士)

ブースターケーブルの接続手順は、赤(+)から繋ぎ、黒(−)は故障車のバッテリーではなくエンジンブロック(アースポイント)に繋ぐという、厳格な4ステップの順序(ジャンプスタート やり方)を厳守しなければなりません。
この手順を守ることで、接続時に発生する可能性のある火花を、バッテリーから遠ざけることができ、引火爆発の危険性を最小限に抑えることができるからです。特に最後の接続をアースポイントに繋ぐことが極めて重要です。
具体的な接続手順(4つのステップ)
(準備と安全対策(3章)が完了し、救援車はエンジンを停止していることを確認してください)。
-
故障車(+)に赤ケーブル接続(赤色+)
赤いブースターケーブルのクリップ(+)を、故障車(上がった車)のバッテリーのプラス端子(+)に、しっかり噛ませます。 -
救援車(+)に赤ケーブル接続(赤色+)
赤いブースターケーブルのもう一方のクリップを、救援車(元気な車)のバッテリーのプラス端子(+)に噛ませます。 -
救援車(-)に黒ケーブル接続(黒色−)
黒いブースターケーブルのクリップ(−)を、救援車(元気な車)のバッテリーのマイナス端子(−)に噛ませます。 -
故障車アースポイントに黒ケーブル接続(黒色−)
・黒いブースターケーブルの最後のクリップを、故障車のエンジンブロック(アースポイント)の金属部(塗装されていない頑丈なボルトなど)に噛ませます。
・警告故障車のマイナス端子(−)に直接接続することは絶対にダメです。引火爆発の原因となります。
始動とブースターケーブルの取り外し手順
- 救援車のエンジンをかけ、5分程度アイドリングさせて、故障車に充電します。
- 故障車のエンジンをかけます。
- エンジンがかかったら、ケーブルを接続時と逆の順序で取り外します。
具体的な取り外し手順(逆の4つのステップ)
- 黒(−)を故障車アースポイントから(火花が飛ぶ可能性があるため、最初に外す)。
- 黒(−)を救援車バッテリー(−)から。
- 赤(+)を救援車バッテリー(+)から。
- 赤(+)を故障車バッテリー(+)から外す。
ひとことまとめ
ブースターケーブルの繋ぎ方の鉄則は、「プラスはバッテリー、マイナスはアース」です。逆接続やショートを避けるため、最後の接続(故障車のアースポイント)を間違えないようにしましょう。
ポータブルジャンプスターター手順
ポータブルジャンプスターター(外部電源、以下ポータブル機)を使用する際も、車同士のジャンプスタートやり方と同様に、極性(+/−)と接続の順番のルールは変わりません。
ポータブル機材も瞬間的に大電流を流すため、逆接続やショートによる電気系統のトラブルや火花発生のリスクは存在します。安全回路(スマートケーブル)が搭載されている製品が多いですが、基本手順を守ることで機器や車両の故障を防ぎます。
具体的な接続手順
-
ポータブル機の電源OFF確認
ポータブル機材の電源が切れていることを確認し、安全クリップを接続します。 -
故障車(+)に赤ケーブル接続(赤色+)
赤ケーブル(+)を、故障車のバッテリーのプラス端子(+)に繋ぎます。 -
故障車アースポイントに黒ケーブル接続(黒色−)
黒ケーブル(−)を、故障車のエンジンブロック金属部(アースポイント)に繋ぎます。 -
ポータブル機の電源ON・始動
ポータブル機の電源を入れ、エンジンを始動させます。 -
取り外し
エンジンがかかったら、接続時と逆の順序で、黒ケーブル(アースポイント)から先に外し、次に赤ケーブル(+)を外します。その後、ポータブル機の電源を切ります。
ひとことまとめ
ポータブル機は救援車を探す手間が省けますが、アースポイントへの接続を省略せずに、必ず基本手順に従って安全にジャンプスタートを行いましょう。
始動後の管理(充電走行・電装OFF)

ジャンプスタートでエンジンが始動した後も、バッテリーはまだ過放電に近い状態です。オルタネーター(発電機)による効率的な充電を促すため、電装品(アクセサリー類)をOFFにした状態で、十分な充電走行を行うことが不可欠です。
エンジン始動直後に電力を多く消費する電装品を使うと、オルタネーターの負担が急増したり、再度バッテリー上がり(過放電)を引き起こす可能性があるからです。
始動後の管理方法
-
電装品の利用制限
エンジン始動後は、ヘッドライト、エアコン、リアデフォッガー(曇り止め)、ワイパーなど、電気を多く消費する電装品をすべてOFFにします。 -
充電走行の実施
短距離走行やアイドリングだけでは不十分です。エンジン回転数が高まる走行(充電走行)を30分〜1時間程度行い、しっかりと充電します。 -
オルタネーターの確認
エンジン回転を上げたときにヘッドライトが明るくなる場合、オルタネーター(発電機)は正常に機能していますが、長期間過放電が続いた古いバッテリーは充電しきれない可能性があります。
ひとことまとめ
ジャンプスタート やり方が成功しても安心せず、電装OFFの状態で充電走行をしっかり行い、早めに専門家によるバッテリー点検を受けましょう。
失敗例と対処(逆接続・発熱・ヒューズ切れ・ECUリセット)
ジャンプスタートが失敗する主な原因は、逆接続やケーブルの不適合、あるいは単なるバッテリー上がりではなく、オルタネーターやスターターモーターなど他の部品の故障が原因である可能性が高いです。異常を感じたら即座に作業を中止し、プロの診断を受けることが安全です。
ブースターケーブルが関わる作業の失敗は、ヒューズ切れや車両の電子制御ユニット(ECU)の損傷など、深刻な二次被害を引き起こす危険性があるため、自力での対処には限界があるからです。
主な失敗例と対処法
| 失敗例 | 原因と症状 | 対処法 |
|---|---|---|
| 逆接続 | プラス(+)とマイナス(−)を間違えたことによるショート。火花や爆発の危険が伴う。 | 即座に接続を解除。絶対に再始動を試みず、ロードサービスを呼ぶ。 |
| ケーブルの異常発熱 | 使用しているケーブルの太さ(許容電流)が不足している、または車両側が極端な大電流を要求している。 | 直ちに接続を解除し、冷えるのを待つ。太いケーブルに交換するか、プロに依頼する。 |
| ヒューズ切れ | 逆接続やショート、または電装品の過負荷によりヒューズ(過電流から回路を守る部品)が切れる。 | ヒューズボックスを確認し、切れたヒューズを同じアンペア数(A)のものに交換。頻繁に切れる場合は配線不良の可能性があり、専門家(プロ)の診断が必要。 |
| ECUリセット/ハンチング | 過放電や電圧変動(サージ電圧)によりECU(エンジン制御ユニット)の記憶内容が消去または損傷し、アイドリングが不安定になる(ハンチング)。 | ECUの再学習やリセットが必要。複雑な手順を要するため、ディーラーまたは整備工場に依頼する。 |
| 始動不良が続く | バッテリー以外の原因(オルタネーター不良、燃料ポンプ不良、プラグの湿気など)。 | 専門知識のないドライバーが原因特定するのは困難です。直ちにロードサービスに連絡し、診断を依頼。 |
ひとことまとめ
電気系のトラブルは、目に見えないECUやヒューズに影響を与えます。高電圧がかかる、または不確実な場合は、必ずプロ推奨の対処を優先しましょう。
アイドリングストップ車の注意(AGM/EFB・学習)

アイドリングストップ車に搭載されるAGM(吸収ガラスマット)やEFB(強化型液式)バッテリーは、通常のバッテリーと異なり、交換時や給電時に特に注意が必要です。給電の際は、指定されたアースポイントやジャンピングポイントを必ず使用してください。
AGMやEFBバッテリーは、大電流の充放電に耐える構造であり、専用の充電制御システム(ECU)によって管理されています。このシステムが電圧の変動や脱着によりリセットされると、アイドリングの学習値が狂い、エンジン不調やエンスト(アイドル不良)の原因となるからです。
AGM/EFB車の特殊な注意点
-
接続ポイント
給電の際は、必ず車両の取扱説明書に従い、バッテリー端子とは別に設けられたジャンピングポイントまたはアースポイントを使用します。 -
学習機能(ECU学習)
バッテリーを脱着したり、過放電が極度に進行した場合、スロットルボディの全閉位置学習(スロットル全開位置学習)や急速TAS学習(アイドル学習)が必要となります。
再学習は特定のヒューズを抜いて行う場合や、専用の診断機を使用する必要があり、専門知識が必要です。
ひとことまとめ
AGM/EFBバッテリー搭載車のジャンプスタートやり方は基本と同じですが、バッテリーの交換や脱着後はECU学習の初期化が必要な場合が多いため、写真台帳などで記録を取り、ディーラーに相談するのが安全です。
HV/EVの扱い(12Vのみ、HV系統は触れない)
HV(ハイブリッド)車やEV(電気自動車)のバッテリー上がり救援では、高電圧による感電や車両の重大な損傷を避けるため、高電圧系統(HV系統)の部品(オレンジ色の配線など)には絶対に触れてはならず、12V補機バッテリーの指定された端子のみを使用して給電を行います。
HV/EV車は、走行用の高電圧バッテリー(数百V)と、通常の電装品を動かすための12Vの補機バッテリーの二つを持っています。ジャンプスタートが必要なのは12V側であり、高電圧部分への給電や接触は命に関わる危険があるからです。
HV/EVの救援における絶対的な安全基準
-
高電圧システムへの非接触
HVシステムウォーニングランプが点灯しているなど、HV系統の異常が疑われる場合は、特に注意が必要です。高電圧関連の部品には絶対触らないでください。 -
給電は12V端子のみ
ブースターケーブルを繋ぐ際は、エンジンルーム内または車両後部に設けられた、12V補機バッテリー専用のジャンピングポイント(またはアースポイント)のみを使用します。
HV車から他の車への救援(電力を提供すること)は、原則として推奨されていません。
ひとことまとめ
HV/EV車のジャンプスタート 手順は非常にデリケートです。高電圧による危険を回避するためにも、12V端子を確認し、不安な場合はプロ推奨のロードサービスを呼びましょう。
ロードサービス比較
バッテリー上がりは、保険付帯のロードサービスやJAF(日本自動車連盟)に依頼することで、迅速かつ安全に解決できます。これらのサービスを利用しても、基本的に等級ダウンの心配はありません。
専門の技術者は、故障診断機や適切な機材を持っており、複雑な電気系統のトラブルや、HV車など特殊な車両にも確実に対応できるからです。また、保険付帯のロードサービスは、料金や事故歴の観点から優位性が高いです。
ロードサービス比較表
(注:料金は概算であり、契約内容や地域、時間帯によって変動する可能性があります。)
| サービス主体 | 特徴 | 到着目安(一般的な場合) | 料金例(ジャンプスタート) | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| JAF | 会員制。非会員でも利用可能。雪道での救援事例も豊富。 | 30分〜1時間前後 | 会員:無料/非会員:1万円〜2万円前後 | 年会費が必要。 |
| 自動車保険付帯 | 契約内容に応じて無料。事故ではないため、通常は等級ダウンしない。 | 提携業者によるため変動あり。 | 契約内容による(無料〜実費) | ロードサービス利用が等級に影響しないか事前に契約確認が必要。 |
| 民間カーレスキュー | 迅速対応を謳う業者が多い。 | 迅速だが地域差が大きい。 | 5,000円〜15,000円程度 | 費用や技術レベルは業者により大きく異なる。 |
自動車保険の等級制度の注意点
自動車保険では、事故を起こして保険を使用すると、翌年3等級ダウンし、保険料が割増になる「無事故割引・事故割増」制度があります。しかし、バッテリー上がりやガス欠などのロードサービス利用は、通常は事故としてカウントされず、等級ダウンの対象外です。
ひとことまとめ
バッテリー上がり手順が不明な場合や危険な状況では、迷わず専門のロードサービスを利用しましょう。保険の契約内容(特にロードサービス料金)を確認し、万が一の事態に備えましょう。
予防と点検(週次チェック・交換サイクル)+FAQ

バッテリートラブルの多くは、日々の簡単な点検(週次チェック)と、オルタネーター(発電機)の異常(オーバーチャージなど)の早期発見、そして適切な交換サイクル(2〜3年)を守ることで予防できます。
バッテリーは電気を蓄えるだけでなく、化学反応により動いています。液量(電解液)の減少や、高温・低温による能力低下は避けられないため、定期的なケアが必要です。
バッテリーの予防と点検ポイント
-
交換サイクル
バッテリーは消耗品であり、寿命は通常2年〜3年です。使用年数が3年を超えている場合は、トラブルが起きる前に交換を検討しましょう。 -
液量チェック(過放電対策)
液式バッテリーは、液面がUPPER LEVELとLOWER LEVELの間(アッパーレベルとローレベルの線)にあるか確認します。液が不足していた場合は、精製水を補充します。
特に夏場はエンジンルームの温度が高くなり、液の蒸発が激しくなるため、液面低下に注意が必要です。 -
端子と配線の点検
端子に白い粉(サルフェーション)が付着している場合は、接触不良の原因となります。
配線が緩んでいないか、腐食していないかを確認します。ターミナル(バッテリー端子)から発生するガスが引火して火花を発生させる危険もあるため、緩みがあればしっかり締め付けます。 -
オルタネーターの点検
バッテリーの過放電だけでなく、オルタネーター(発電機)の故障(ICレギュレーターの調整不良やVベルトの緩み・切れなど)も、バッテリー上がりの原因となります。 Vベルトが切れると、オルタネーターが回らず発電できなくなります。ベルトの緩みや劣化がないか定期的にチェックしましょう。
ひとことまとめ
日々の点検(特に液量と端子の状態、Vベルト)と、交換サイクル(2〜3年)を意識し、早めの対策を行いましょう。
FAQ(よくある質問)
Q1:ブースターケーブルの繋ぎ方を間違えて逆接続したらどうなりますか?
A1:逆接続はショート(短絡)を引き起こし、火花が発生します。この火花がバッテリーから発生する水素ガスに引火すると爆発の危険があります。また、ECUなどの電子制御ユニットに過大な電流が流れ、ヒューズ切れやシステム故障につながる可能性が高いです。すぐにケーブルを外し、絶対にエンジン始動を試みず、ロードサービスを呼んでください。
Q2:ブースターケーブルは赤と黒が+/−ですか?接続手順を教えてください。
A2:ブースターケーブルは通常、赤色がプラス(+)、黒色がマイナス(−)です。接続は、1. 故障車(+) → 2. 救援車(+) → 3. 救援車(-) → 4. 故障車のエンジンブロック(アースポイント)の順で行います。外す際は、この逆の手順で行います。
Q3:HV/EV車のバッテリー上がりの対処は、自分でやっても大丈夫ですか?
A3:HV/EV車(ハイブリッド/電気自動車)には高電圧システム(HV系統)が搭載されています。高電圧系統に触れると感電の危険があるため、自分で作業をする場合は、必ず12V補機バッテリーの指定された端子のみを使用してください。不安な場合は、車両の取扱説明書を確認するか、専門のロードサービスに依頼することを強く推奨します。
Q4:ロードサービス 料金はどれくらいかかりますか?
A4:ロードサービスの料金は、サービス主体や会員/非会員の別で大きく異なります。JAF会員や自動車保険にロードサービスが付帯している場合、ジャンプスタートは無料となることが多いです。非会員の場合、業者や時間帯によっては費用(数千円〜1万円以上)がかかることがあります。保険付帯サービスは等級ダウンの心配が少ないため、事前に契約内容を確認しておきましょう。
Q5:過放電後、どのくらい充電走行すれば良いですか?
A5:ジャンプスタート後、バッテリーはまだ十分には充電されていません。オルタネーター(発電機)からの充電を促すため、エアコンやライトなどの電装品をOFFにして、30分から1時間程度、走行(充電走行)を続けることが推奨されます。短時間の走行やアイドリングだけでは不十分です。
安全・復旧のためのチェックリスト
-
安全確認チェックリスト
[ ] 路上安全を確保しましたか?(ハザード点灯、三角表示板または発炎筒設置)
[ ] 雨天や水たまり、電線近くでの作業を避けていますか?
[ ] 両車ともにPレンジ、サイドブレーキを引きましたか?
[ ] 両車の電装品(アクセサリー類)をすべてOFFにしましたか?
[ ] 保護具(メガネ・手袋)を着用しましたか?
[ ] 救援車のエンジンを止めましたか?
-
持ち物・準備品チェックリスト
[ ] ブースターケーブル(ディーゼル車の場合は太いもの)。
[ ] 車両の取扱説明書(HV/アイドリングストップ車の場合は接続箇所確認のため)。
[ ] ロードサービスの連絡先(保険会社またはJAF)。 -
正しいブースターケーブル繋ぎ方(車同士)チェックリスト
接続順(必ずこの順序で繋ぐ) - 赤(+)を故障車バッテリー(+)に。
- 赤(+)を救援車バッテリー(+)に。
- 黒(−)を救援車バッテリー(−)に。
- 黒(−)を故障車のエンジンブロック(アースポイント)に。(NG 故障車バッテリーのマイナス端子に繋いでいませんか?)
始動後(この順序で外す:逆接続による火花を防ぐため)
- 黒(−)を故障車のエンジンブロック(アースポイント)から先に外す。
- 黒(−)を救援車バッテリー(−)から外す。
- 赤(+)を救援車バッテリー(+)から外す。
- 赤(+)を故障車バッテリー(+)から外す。
-
NG行為チェックリスト
[ ] HV/EV車の高電圧系統(オレンジ色の配線)を触る。
[ ] 故障車のマイナス端子(−)に黒ケーブルを直接繋ぐ。
[ ] エンジン始動後、すぐに電装品をフル稼働させる。
[ ] 異なる電圧の車同士でジャンプスタートを試みる。
[ ] ブースターケーブルの接続順を無視する。

最短30分で駆けつけます!
車の故障・パンク・事故車のけん引など、
車のトラブルは「カーレスキュー隊24」に
お任せください。
便利なお支払い方法も充実!
-
現金OK

-
カード払いOK

-
後払い決済OK








