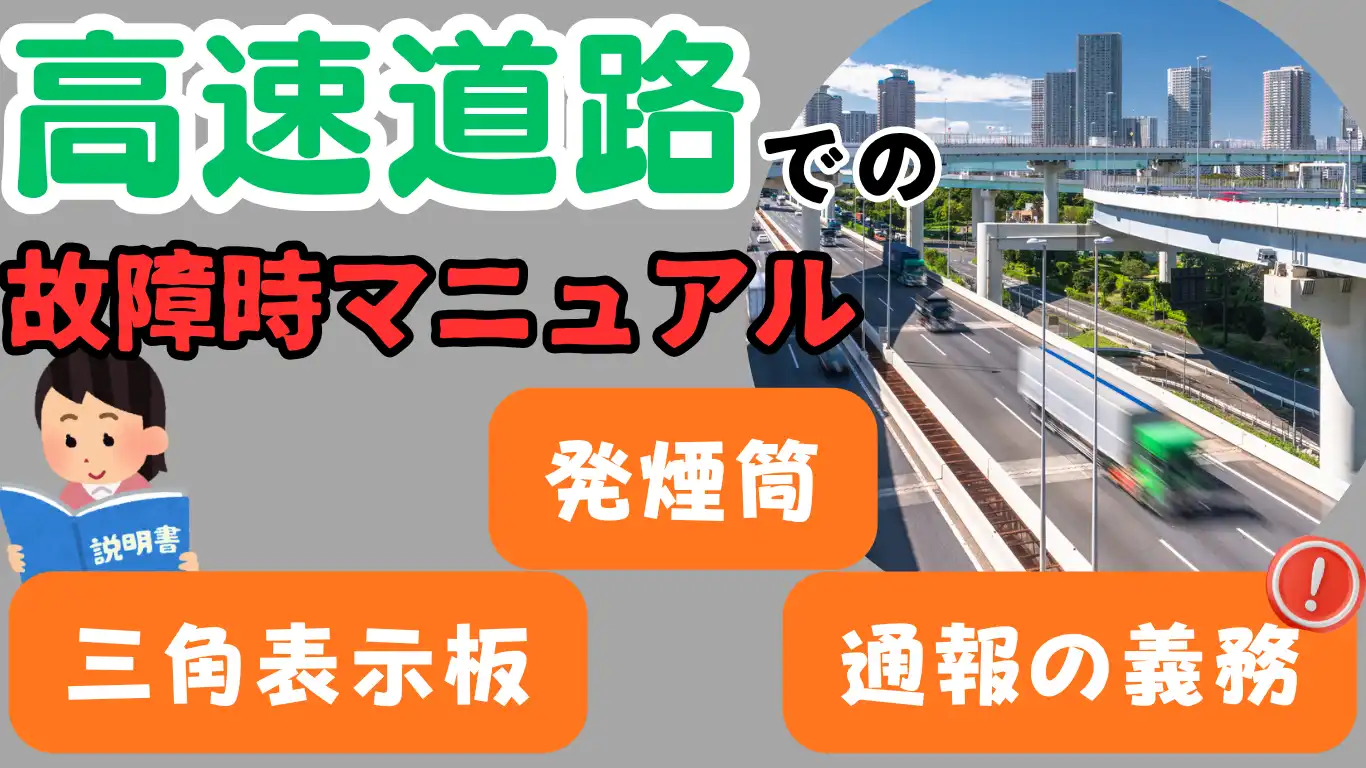
高速道路での「もしも」の故障時、人命と二次事故を防ぐための高速道路 故障 対応マニュアル。発炎筒使い方、三角表示板距離の設置方法、高速通報方法を専門ライターがやさしく解説します。万が一に備え、ロードサービス要請の手順も確認しましょう。
まず最優先:命を守る(車外退避 → 後方警戒 → 通報の順)

高速道路で車が停止した場合、「人命の安全」が最優先です。車外へ退避し、後続車への警戒を素早く行うことがすべてに先立ちます。
高速道路上での停車は、一般道と比較して二次事故に巻き込まれるリスクが極めて高いためです。特に停止直後の車内に留まる行為は、後続車による追突事故が発生した場合、重大な人身事故につながる可能性が高く危険です。
具体的な行動順序
- 車外へ退避:停車後、速やかに全員が車外へ出ます。
- 後方警戒(表示):ハザードランプ点灯に加え、発炎筒や三角表示板を使用して、後続車に故障車の存在を知らせます。
- 通報:安全な場所へ退避してから、非常電話または携帯電話でロードサービス 要請や警察への通報を行います。
命を守る最優先のステップは、「退避」です。ガードレール外など、安全な場所に避難してから次の行動に移りましょう。
安全に停めるポイント:ハザード・左側寄せ・路肩・斜め停車のコツ

故障を察知したら、路肩(ハードショルダー=高速道路の路肩)にできる限り左側に寄せて停車し、ハザード(非常点滅灯)を点灯させましょう。
車線内に停止することは非常に危険です。後続車に危険を知らせるため、また、救援車両(レッカー車やロードサービス)が安全に作業できるスペースを確保するためです。
具体的な停車手順
- ハザード点灯:異常を感じたらすぐにハザードランプを点灯させ、周囲の車に異常を伝えます。
- 路肩へ移動:惰性やわずかな力を使ってでも、可能な限り左側の路肩に寄せます。
- 斜め停車は厳禁(一般論として):走行車線に車の後部がはみ出したり、車体が斜めになったりすると、追突の危険が増します。可能な限り車体は道路と平行に路肩に寄せましょう。
- エンジン停止と施錠:エンジンを停止し、キーを抜いて(最近の車種はキーをオフにする)、サイドブレーキを確実にかけます。車から離れる際、ロックを忘れずに。
路肩(路肩=舗装された道路の端のスペース)に寄せられない場合:
もし路肩が狭く、車線内に停止せざるを得ない場合は、ハザード点灯に加え、発炎筒や三角表示板をすぐに設置し、躊躇なくガードレール外へ退避してください。
異常を感じたら、ハザードを点け、路肩の最も安全な場所に停車し、エンジンを止めて退避準備をしましょう。
夜間・雨天・トンネル内の注意:見え方が悪い時にやること

夜間、雨天、トンネル内など、視界が悪い状況での高速道路故障対応は、昼間以上に後方警戒の重要性が増します。
視界不良時には、後続車の発見が遅れ、追突のリスクが劇的に高まるからです。特に夜間やトンネル内では、車両の存在を示す灯火類や反射材の効果が最大限に発揮されるよう努める必要があります。
状況別の具体的な注意点
-
夜間:
・ハザードランプを点灯させたまま、停車灯や尾灯(テールランプ)も点灯させておきます。
・発炎筒や三角表示板の設置は必須です。発炎筒は炎の光で視認性が非常に高いです。
・安全ベストや反射材付きの衣服を着用し、作業者の視認性を高めます。 -
雨天・霧:
・路肩のぬかるみや、水しぶきによる視界悪化に注意し、退避場所も慎重に選びます。
・故障によりワイパーが動かない場合、速やかに路肩に寄せる必要があります。ワイパーのトラブルはヒューズ切れやアームの緩み、モーター不良などが原因で起こることがあります。 -
トンネル内:
・非常電話は通常、100mおきに設置されています。これを利用して通報しましょう。
・発炎筒の使用は、煙が充満する可能性があるため、道路管理者や警察の指示に従う必要があります。三角表示板の設置がより重要になります。
見え方が悪い時ほど、ハザード、発炎筒、三角表示板といった後方警戒の装備を惜しまずに使用し、速やかにガードレール外へ退避しましょう。
発炎筒の使い方:取り出し→点火→設置場所と向き

発炎筒(自動車用緊急保安炎筒)は、車両の存在を後続車に強く知らせるための法令で携行が義務付けられている赤い炎を出す筒です。
発炎筒の赤い光は、昼夜を問わず非常に視認性が高く、後続車に対して「危険が迫っている」という強い警告信号を発するため、二次事故防止に最も効果的だからです。
発炎筒使い方(点火と設置)
-
取り出し:
・通常は運転席の足元(または助手席のグローブボックス内)にあります。
・車外に出る際、発炎筒と三角表示板、携帯電話を必ず持って出ましょう。 -
点火手順:
・キャップを回して外し、筒の底にあるマッチ状の擦り薬をキャップの先端で擦って点火します。
・点火する際は、煙や火花を避けるため、顔や衣服から離して行います。 -
設置場所と向き:
・車両の後方、一般的な目安として50〜100m程度離れた場所(交通の状況や地形に応じて調整)の路肩外寄りに置きます。
・発炎筒の点灯時間の目安は数分〜十数分程度(製品指定による)ですが、その間に次の安全措置(三角表示板設置、非常電話で通報)を完了させる必要があります。
発炎筒は高速道路故障対応における後方警戒の切り札です。点火したら、すぐに路肩外側の安全な場所に設置しましょう。
三角表示板の設置:一般的目安距離(例:50〜100m)と地形に応じた調整

三角表示板は、発炎筒と並び、故障車両の後方警戒のために法令により設置が推奨される(高速道路上では停止表示器材の設置が義務)重要な器材です。
三角表示板は夜間でも反射材によって後続車に視認されやすく、発炎筒が燃え尽きた後も車両の存在を示し続けることができるからです。
三角表示板の一般的目安距離と設置
| 項目 | 目安 | 設置時の注意点 |
|---|---|---|
| 表示板の距離 | 後方50〜100m(一般的目安) | 設置時に路肩を歩く際は、ガードレール外側を歩くのが原則。 |
| 発炎筒の設置 | 車から少し後方・路肩外寄り | 路肩または停止帯に停車できない場合は、より長く(遠く)に設置。 |
| 点灯時間の目安 | 数分〜十数分(製品表示に従う) | 三角表示板は恒久的な警告となる。 |
地形に応じた距離の調整
-
上り坂やカーブ(見通しが悪い場所)
後続車が停止車両を視認できる時間が短いため、表示板の距離を100m以上など、より長く確保する必要があります。 -
トンネル内
・非常電話付近や、照明の届く範囲の路肩外寄りに設置します。
・三角表示板を設置するために走行車線に出る行為は、二次事故を招くため極めて危険であり、必ずハザードを点灯させ、周囲に細心の注意を払う必要があります。
三角表示板は、高速道路故障対応における後方警戒を継続させるための重要アイテムです。路肩を歩く際は、命を守るため、ガードレール外側を優先しましょう。
通報の実務:非常電話・スマホ通報・位置の伝え方(キロポスト等の読み方)

高速通報方法の基本は、非常電話(緊急時に道路管制センターへ直通で繋がる電話)の利用です。これにより正確な位置情報を迅速に伝えることができます。
非常電話は、受話器を取るだけで道路管制センターへ直通し、電話の設置場所がそのまま故障車両の位置となるため、迅速なロードサービス 要請や警察・消防への連携が可能です。携帯電話(スマホ)は位置特定に時間を要することがあります。
通報の実務と位置の伝え方
-
非常電話の利用
・高速道路やトンネル内に1kmごと(または500mごと)に設置されています。
・非常電話まで歩く際は、ガードレール外側(路肩の外側)を歩き、絶対に車線側にはみ出さないように注意します。 -
携帯電話での通報
・携帯電話(スマホ通報)で通報する際は、現在地を正確に伝えることが重要です。
・キロポスト(=高速道路の距離表示:例「東京から200km地点」を示す標識)や橋梁、トンネル、最寄りのIC名(インターチェンジ名)の情報を伝えましょう。
通報時に伝えるべき情報
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 場所 | 高速名・上下線・キロポスト・近いIC名 |
| 状況 | 停車位置・発煙/事故の有無・負傷者の有無 |
| 車両 | 色・車種・台数 |
| 安全措置 | ハザード・三角表示板・発炎筒・退避の実施状況 |
通報時は、命の危険を伝え、次にキロポストなどの位置情報を正確に伝えることで、レッカーやロードサービスの到着時間を短縮できます。
同乗者・子ども・ペットの避難:歩く位置・待機場所・服装(反射材)
ドライバーだけでなく、同乗者や子ども、ペットを含めた全員が、ガードレール外側や路肩の外側にある安全な場所へ速やかに退避することが、二次事故を防ぐための基本です。
停車車両のそばは、時速100km近いスピードで走る後続車に巻き込まれる可能性が常にあり、最も危険な場所だからです。車外に出た後も、走行車線側に留まることは避けなければなりません。
同乗者の安全確保
-
降りる方向:
車線と反対側のドア(助手席側または左側)を使って降ります。走行車線側のドアは絶対に開けてはダメです。 -
歩く位置:
ガードレール外側、または路肩の最も外側を、後方警戒のため車や人が上流側(後方)に立たないよう、風下へ向かって歩きます。 -
待機場所:
ガードレール外側にある安全な場所に集まります。柵がない場合は、路肩の最も外側に身を寄せます。 -
子どもや高齢者:
パニックを起こしやすい子どもや高齢者は、必ず大人が手を引いて移動させます。
服装と視認性(反射材)
夜間や悪天候時を想定し、トランクなどに安全ベストや反射材(反射材=光を反射する素材)のついた衣服を携行しておくと、視認性が向上し安全です。
全員が車から離れ、ガードレール外で待機することが、高速道路 故障 対応における最大の安全対策です。
タイヤ・オーバーヒート・燃料切れ別の一次対応:やってよい/ダメ

高速道路での故障は多岐にわたりますが、いずれのケースも路上作業は原則的に避け、まず安全確保(退避)と通報を行い、レッカー車やロードサービスの到着を待つのが鉄則です。
高速走行中にトラブルが発生した場合、その原因(エンジン系、駆動系、タイヤなど)をドライバーが特定・修理するのは非常に困難かつ危険だからです。無理な作業は二次事故を招きます。
故障別の一次対応(やってよい/ダメ)
| 故障の種類 | 症状の例 | やってよいこと | やってダメなこと |
|---|---|---|---|
| タイヤのパンク/損傷 | 異音、ハンドルが取られる、タイヤがガタガタ振動を始めた。 | ハザード点灯、路肩へ停車。安全な場所への退避。 | 路肩でのタイヤ交換(ジャッキアップ)。空気圧が低いまま高速走行を続けること。 |
| オーバーヒート | エンジンからキンキン音、カリカリ音がする。水温計がレッドゾーンを示す。 | エンジン停止し、車外退避。ボンネットを開けず冷却を待つ。 | ラジエターキャップを開ける(熱湯噴出で火傷の危険)。冷却水(ラジエター液)を補充すること。 |
| 燃料切れ | エンジン停止、またはエンストを繰り返す。 | 路肩へ停車し、退避後ロードサービス要請。 | 車を降りてガソリンスタンドまで歩く(危険)。 |
| バッテリー上がり | エンジン始動せず、カチカチ音がする。ライトが暗い。 | ロードサービスを呼び、救援を待つ。 | 高速道路でのジャンプスタート作業(ケーブル接続は複雑で危険)。 |
エンジン故障の初期症状
エンジン故障は、異音や異臭で気づくことが多いです。例えば、エンジン回転を上げると「キルキル音」(ベルトの滑り)、回転が重く「コロコロ音」(メタル部品の摩耗)、加速中に「バカン」「バスン」音(点火系の不具合)、または「甘いワインの臭い」(冷却水漏れ)などが挙げられます。これらの異常を感じたら、速やかに安全な場所に停車すべきです。
高速道路上での路上作業は極力避け、牽引や修理は専門業者へ依頼しましょう。
EV/HVの注意:高電圧に触れない・緊急遮断の基本・発煙時の距離
EV(電気自動車)やHV(ハイブリッド車)の故障対応は、高電圧システム(HV系統)による感電や火災のリスクがあるため、通常のガソリン車以上に細心の注意が必要です。
これらの車両は、走行用のメインバッテリーに数百ボルトの高電圧電流が流れています。整備士は専門の知識と訓練を積んで作業しますが、一般のドライバーが不用意にHV系統(オレンジ色の高電圧配線等)に触れると、重大な事故につながるためです。HV車では、インバータ冷却系統の異常を示すHV故障コードが検出されるなどのトラブル事例もあります。
EV/HV車での絶対禁止事項と緊急対応
-
高電圧部分への非接触:
・ボンネットを開けても、オレンジ色の配線や部品には絶対に触れないでください。これらがHV系統を示しています。
・車両に「ハイブリッドシステムウォーニングランプ」などの警告灯が点灯している場合は、HVシステムの異常を示唆しています。 -
緊急遮断(メイン電源OFF):
故障や発煙・火災の兆候が見られた場合は、キー(またはパワースイッチ)をOFFにし、必要であれば車両の取扱説明書に従い、メインヒューズやサービスプラグ(メインバッテリーの電源を遮断する部品)を操作して、電力供給を遮断します。 -
発煙・火災時の退避距離:
高電圧バッテリーは熱暴走を起こすと、激しい火災になる可能性があります。車外へ退避した後、通常よりもはるかに離れた安全な距離(最低でも100m以上など)を確保して非常電話で通報しましょう。
EV/HV車での高速道路故障対応は、高電圧という潜在的な危険があります。可能な限り運転を避け、ロードサービスの到着を待つのが賢明です。
レッカー・ロードサービスの呼び方:保険付帯/JAF等/ディーラー比較

高速道路故障対応の専門的な解決手段は、ロードサービス要請です。多くのドライバーは、自動車保険やJAFなどの保険付帯サービスを利用できます。
高速道路での牽引や修理は専門的な知識と大型機材(レッカー車など)が必要であり、個人での対応は危険です。また、多くの自動車保険には無料で利用できるロードサービスが含まれているため、費用面でも利用すべきです。
ロードサービス比較(一般的な目安)
| サービス | 特徴 | 到着目安(一般的な場合) | 費用の幅 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 保険付帯 | 契約内容に応じて無料。等級ダウンの心配なし。 | 30〜60分 | 契約により無料枠 | 牽引距離や回数に制限がある場合がある。 |
| JAF等 | 会員制。非会員でも利用可能。高い技術力。 | 30〜90分 | 会員:無料/非会員:1万円〜3万円 | 年会費が必要。保険会社のロードサービスと併用可能。 |
| ディーラー | 車両保証やリコール(無料修理)の対象になる可能性。 | 要相談 | 規定工賃(保証適用外の場合) | 営業時間外や長距離牽引には対応できない場合がある。 |
通報時のポイント
ロードサービスに連絡する際は、非常電話やキロポストで確認した正確な場所(高速名・上下線・IC間など)と、車の状態(エンジンがかからない、タイヤ パンクなど)を正確に伝えましょう。
ほとんどのトラブルはロードサービスで対応可能です。まずは加入している自動車保険の連絡先やJAFの番号を思い出しましょう。
費用と到着時間の目安:時間帯・場所・作業内容での幅

ロードサービスの料金や到着時間は、場所(都市部か山間部か)や時間帯(昼間か夜間か)によって大きく変動します。
都市高速や主要な大動脈では、レッカーの出動拠点が近いため到着時間が短い傾向がありますが、深夜や山間部では出動に時間がかかり、費用が高くなる可能性があるからです。
ロードサービス 料金と到着時間の目安
(注:以下の費用と時間は一般的な目安であり、実際の料金は契約や状況によります。)
| 項目 | 目安の範囲 | 影響を与える要因 |
|---|---|---|
| ロードサービス到着時間 | 30分〜1時間半 | 交通状況、天候(雨天・積雪)、場所(都市部/山間部)、夜間。 |
| 基本料金(非会員・非保険) | 10,000円〜30,000円 | レッカー移動距離(例: 10kmまでは無料、超過分は有料)、夜間/早朝の割増。 |
| 保険付帯の費用 | 0円〜5,000円程度 | 牽引距離が契約上限を超過した場合のみ実費。 |
| 作業費(現場修理可能な場合) | 0円〜15,000円程度 | パンク応急修理、バッテリー上がりのジャンプスタートなど。 |
保険の適用範囲
自動車保険のロードサービスは、牽引距離(例: 50kmまで無料)やサービス内容に上限が設けられていることがあります。特に長距離の牽引が必要な場合は、事前に保険会社に確認しましょう。また、事故ではないバッテリー上がりや燃料切れなどでもサービスを利用できる場合が多いです。
ロードサービス料金は、保険付帯であれば大半が無料です。高速 通報 方法の際に到着時間も確認しておきましょう。
よくある失敗と二次事故回避:車内待機・逆走・無理なタイヤ交換など

高速道路での故障時、ドライバーが安全のために行うべき行動と、二次事故を招くやってはいけない失敗例を明確に理解することが重要です。
焦りやパニックから誤った判断(特に車内待機や路上での作業)をしてしまい、命を危険にさらすケースが多発しているからです。
高速道路でやってはいけない危険な失敗例
-
車内での待機:
停止した車内、特に路肩に停車した車内に留まるのは、二次事故(追突)の危険があるため絶対にダメです。すぐにガードレール外へ退避しましょう。 -
不用意な路上作業:
路肩で自分でタイヤ交換を試みたり(ジャッキアップは転倒リスク高)、エンジンルームを開けて修理を試みたりする行為は、他の車の往来により非常に危険です。路上作業は極力避け、牽引・修理は専門業者へ任せます。 -
表示板設置のための逆走:
三角表示板や発炎筒を設置する際、車線と並行して後方へ歩くことはやむを得ませんが、逆走(車の進行方向とは逆へ歩くこと)は交通の妨げになる可能性があります。常にガードレール外を歩くことを心がけ、後方警戒を怠らないこと。
二次事故回避の鉄則
車両故障の原因によっては、走行中に車輪がガタガタ振動を始めたり、ウォーウォー音(ベアリングのオイル不足)がしたり、変速機(トランスミッション)にオイル漏れが起こったりと、走行不能になる前の予兆がある場合が多いです。異変を感じたら、安全に停車しロードサービス 要請しましょう。
故障時、車内待機は生命の危険に直結します。退避と後方警戒(三角表示板、発炎筒)を最優先し、自力での路上作業は極力避けましょう。
まとめと携行品チェックリスト:必携品・点検周期・FAQ(Q1〜Q5)
高速道路故障対応で最も重要なのは、「人命優先」の原則と、「三角表示板」「発炎筒」といった安全装備の準備と正確な使用です。
万全な事前準備があれば、パニックに陥ることなく、安全な手順を踏んで二次事故を回避し、迅速にロードサービス 要請に繋げることができるからです。
日頃の点検と携行品
-
必携品チェックリスト:
・[ ] 発炎筒(有効期限内のもの)
・[ ] 三角表示板(法令で設置義務)
・[ ] 携帯電話(非常電話より便利だが、位置特定に注意)
・[ ] 懐中電灯(夜間やトンネル内用)
・[ ] 安全ベストまたは反射材付きの衣服(特に夜間の視認性確保) -
点検周期の目安:
・タイヤ:空気圧のチェック、亀裂や摩耗(スリップサイン)の確認(走行前の点検)
・エンジンオイル:量の確認、交換サイクル(一般的な乗用車で5,000kmまたは6ヶ月〜1年ごと)を守る。
・ベルト:緩みや亀裂がないか、異音(キュルキュル音)がないか確認。
「高速道路故障対応」は事前の準備が8割です。安全装備を必ず携行し、いざという時の高速通報方法を頭に入れておきましょう。
FAQ(よくある質問)
Q1:高速道路で車が止まった場合、非常電話と携帯(スマホ通報)どちらが早いですか?
A1:非常電話は受話器を取るだけで道路管制センターに直通し、自動でキロポストなどの位置情報が伝わるため、通報としては最も迅速かつ正確です。携帯電話も使えますが、現在地(キロポスト、IC名など)を正確に伝える必要があります。安全確保後、最も近い方を利用しましょう。
Q2:発炎筒を設置する距離の目安は?また、設置は危険ではないですか?
A2:三角表示板および発炎筒は、一般的に後方50〜100m程度(道路交通法に基づき50m以上)の路肩外寄りに設置します。設置のために走行車線に出るのは非常に危険です。設置に向かう際は、必ずハザードを点灯させ、ガードレール外側を歩いて移動し、二次事故の危険を回避しましょう。
Q3:ロードサービス 要請時、保険を使うと等級ダウンしますか?
A3:バッテリー上がり、ガス欠、キー閉じ込みなどのロードサービスは、通常、事故(保険金支払い対象となる事故)としてはカウントされず、自動車保険の等級ダウンの対象外です。安心して利用してください。ただし、事故や車両保険を使用する場合は等級ダウンの可能性があります。
Q4:高速道路 故障 対応で、路肩でのタイヤ交換や修理は自分でやっても大丈夫ですか?
A4:路肩での路上作業は極力避け、専門業者へ依頼しましょう。高速走行中の車両による風圧や接触の危険があり、特にジャッキアップしてのタイヤ交換は大変危険です。人命の安全を最優先し、退避後にレッカーを呼びましょう。
Q5:EV/HV車が故障した際、高電圧システムに注意すべき点は?
A5:EV/HV車には数百ボルトの高電圧が流れるHV系統があります。オレンジ色の配線には絶対に触れないでください。発煙や火災の危険があるため、退避したら車両から十分な距離をとり、非常電話で通報し、レッカー到着を待ちます。
携行品チェックリスト
| 項目 | 状態/場所 | 必須度 |
|---|---|---|
| 発炎筒 | 有効期限内ですか? | ◎ 必須(法令で携行義務) |
| 三角表示板 | すぐ取り出せる場所にありますか? | ◎ 必須(高速道路で設置義務) |
| 携帯電話/充電器 | 非常電話が見つからない場合に備えて | ◎ 必須 |
| 安全ベスト/反射材 | 夜間の路肩歩行時に着用 | 〇 推奨 |
| 懐中電灯 | 夜間、三角表示板の設置や移動時に | 〇 推奨 |
| ロードサービス連絡先 | 保険会社またはJAFの番号 | ◎ 必須 |
NG行為チェックリスト
- [ ] 車内や路肩に留まっていませんか?(二次事故リスク)
- [ ] 走行車線側のドアを開けていませんか?
- [ ] 三角表示板や発炎筒を設置せずに車を離れていませんか?
- [ ] 路肩でタイヤ交換やエンジン修理を試みていませんか?
- [ ] 人や車の上流側(後方)に立っていませんか?
- [ ] EV/HV車のオレンジ色の配線に触れていませんか?

最短30分で駆けつけます!
車の故障・パンク・事故車のけん引など、
車のトラブルは「カーレスキュー隊24」に
お任せください。
便利なお支払い方法も充実!
-
現金OK

-
カード払いOK

-
後払い決済OK








