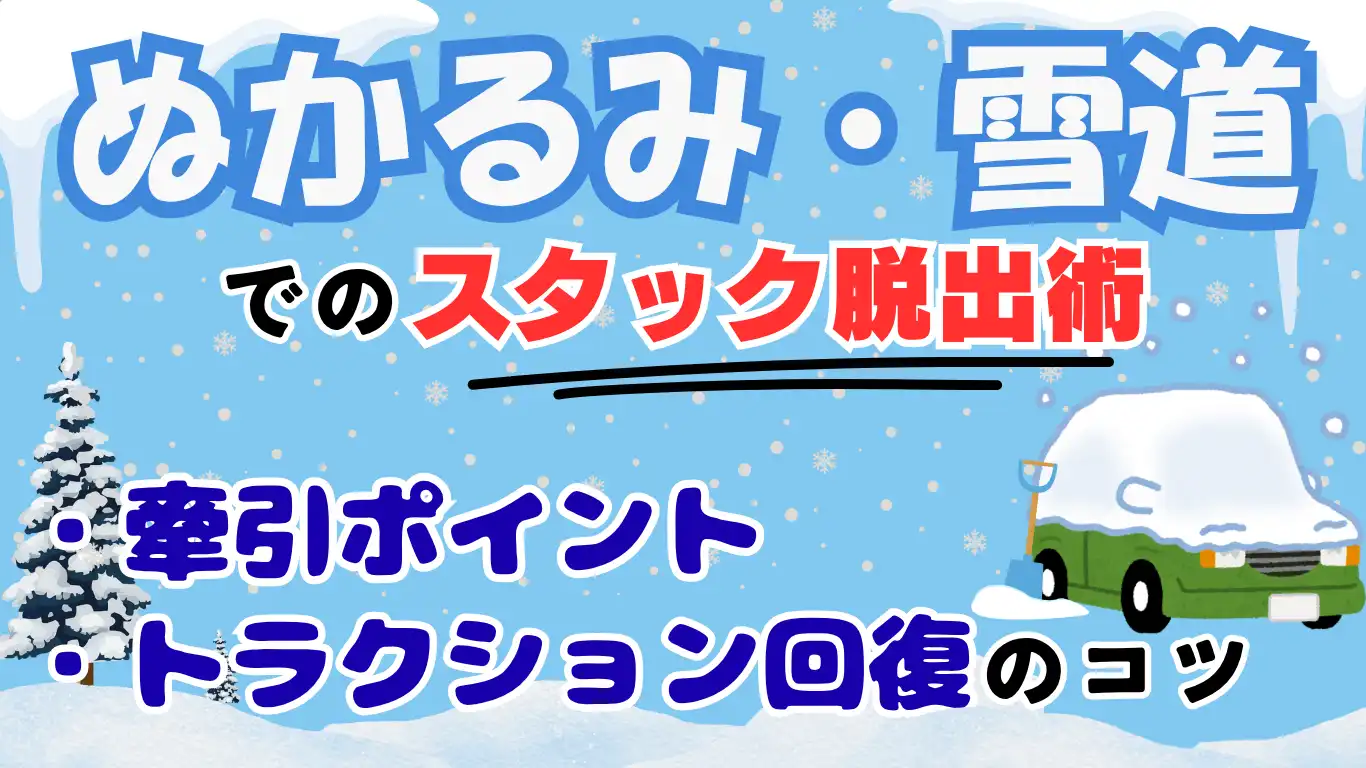
スタック 脱出を安全に行うためのマニュアル。雪道 ぬかるみ 牽引が必要な時の手順、トラクション 回復のためのコツ、牽引ポイント 車の見つけ方、そしてプロへのロードサービス 依頼基準を専門家が解説します。
安全確保→状況把握→“滑らせない・掘らない”が基本、無理はせず救援要請

ぬかるみや雪道でスタックした場合、最優先は安全確保と状況把握です。自力脱出の基本は、タイヤを空転(=タイヤが滑って空回りすること)させず、路面を掘らないよう慎重にトラクション 回復を試みることです。
空転を続けると、タイヤがますます泥や雪の中に深く沈み、脱出が絶望的になるだけでなく、タイヤや駆動系(デフロックなど)に負荷がかかり故障の原因となるからです。また、人や車両の安全が確保できない状況での作業は、二次事故を招くため無理をせずプロに救援を要請する必要があります。
具体例
深い雪道でスタックし、アクセルを強く踏み込んでしまうと、タイヤが空転し、雪や泥が勢いよく飛び散り、周りの人や車に危険が及ぶだけでなく、タイヤの熱で周囲の雪を溶かし、氷にしてしまい、さらに状況が悪化します。このような時は、一度アクセルから足を離し、落ち着いて路面の状況を診断し直す必要があります。
ひとことまとめ
スタック 脱出の鉄則は「空転させず、掘らない」ことです。安全が最優先であり、無理だと感じたらロードサービス 依頼を検討しましょう。
初動の安全:停止位置・三角表示板・乗員退避・夜間の反射材

スタックした場所が危険な場合は、速やかにハザードランプを点灯させ、同乗者を退避(=安全な場所へ避難)させ、後続車への後方警戒を行います。
ぬかるみや雪道でのスタックは、天候が悪く視界が悪い状況で発生しやすいため、後続車による二次事故のリスクが高まります。特に夜間や視界不良時には、ドライバーや同乗者が安全な場所へ退避し、反射材を着用して視認性を高めることが人命を守るために不可欠です。
具体的な初動の安全手順
- ハザード点灯:停止したらすぐにハザード(非常点滅灯)を点灯させます。
- サイドブレーキとPレンジ:サイドブレーキをかけ、オートマチック車はP(パーキング)レンジ、マニュアル車はギアを1速かR(リバース)に入れておきます。寒冷地では、サイドブレーキワイヤの凍結(=ワイヤー内部に水が入り凍り付くこと)により、サイドブレーキを解除できなくなるトラブルが発生することがあるため、注意が必要です。
- 乗員退避:ガードレール外側など、安全な場所へ全員が退避します。
- 後方警戒:安全三角表示板や発炎筒(=緊急時に赤い炎で危険を知らせる筒)があれば、後続車に停止車両の存在を知らせるため、安全な距離を確保して設置します。
- 夜間・悪天候時の視認性:反射材付きの衣服や安全ベストを着用し、懐中電灯などで自分の存在を周囲に知らせます。
ひとことまとめ
スタック場所が危険な場合は、脱出を試みる前に、まず乗員全員の退避と後方警戒を完了させましょう。
状況診断:どの車輪が沈んだか/路面の種類(泥・粉雪・圧雪・氷)/勾配の有無
スタック脱出を成功させるには、闇雲にアクセルを踏むのではなく、どの路面(泥、雪、氷)で、どの車輪(駆動輪か非駆動輪か)が沈んでいるかを正確に把握する状況診断が必要です。
路面やスタック状況によって、トラクション 回復のために行うべき対応策(例:空気圧調整、足場作り、牽引)が根本的に異なるからです。例えば、雪道の中でも粉雪と圧雪(=雪が踏み固められた状態)では、タイヤが路面を掴む力(トラクション)が全く違います。
具体的な状況診断のチェックポイント
-
駆動輪の特定:
・FF車(前輪駆動)やFR車(後輪駆動)の場合、空転している車輪が駆動輪かどうかを確認します。
・4WD(四輪駆動)でも、デフロック(=左右のタイヤの回転差を制限する機構)がない場合、空転しているのは通常、1輪か2輪です。 -
路面の状態:
・泥:タイヤが泥の中に完全に埋没しているか、車底(腹)が接地しているか。
・粉雪:踏み固まっておらず、タイヤがグリップしにくい。
・圧雪・凍結:固い雪道や氷はグリップ回復が難しいため、タイヤチェーンなどの滑り止めが必須。 -
車両の状態:
・車底が地面(または雪や泥)に触れていないか(車底接地)。車底が接地している場合は、タイヤに荷重(重さ)がかからずトラクションがゼロになります。
・勾配(傾斜)の有無。上り坂でのスタックは特に脱出が困難です。
ひとことまとめ
スタック 脱出は、まずは目視で沈んでいるタイヤと、路面の種類(雪道 ぬかるみ)を冷静に診断することから始まります。
トラクション回復の基本技(段階別):空気圧を少し下げる・前後に小刻み揺すり・発進ギアの選択
自力でのスタック脱出を試みる場合、トラクション回復のために空転を避け、タイヤを路面に噛ませるための基本的なテクニック(空気圧調整、小刻み揺すり)を段階的に試します。
空転はトラクション(=タイヤが地面をつかむ力)を失う最大原因です。雪や泥の上でタイヤをわずかに滑らせることで、タイヤの接地面(路面と触れる部分)を広げたり、足場を作ったりする効果が期待できます。
トラクション回復の基本技
-
発進ギアの選択:
・オートマチック車の場合は、Dレンジ(ドライブ)ではなく、2速やスノーモード(=低速で発進するための車載モード)など、低めのギアを選択し、アクセルを極力優しく踏みます。
・マニュアル車は通常2速(またはローモード)で発進し、エンジン回転数を低く保ちます。 -
前後に小刻みに揺すり(空転回避):
・低速ギアに入れた状態で、アクセルを軽く踏み込み、前進(D)と後退(R)を交互に繰り返します。
・空転が始まったと感じたら、すぐにアクセルから足を離すのがコツです。これを繰り返すことで、タイヤの前後(進行方向)に踏み固められた足場(トラクション 回復のための道)を作り、その勢いを利用して脱出を試みます。 -
空気圧を少し下げる(泥・深雪の場合):
・ぬかるみや深雪の場合、タイヤの空気圧を通常より10〜20%程度(例:2.0kg/cm²→1.6〜1.8kg/cm²)下げてみます(取扱説明書に記載の許容範囲内で行いましょう)。
・理由:空気圧を下げるとタイヤの接地面が広がり、接地トラクションが向上します。
・注意:脱出後は、すぐに安全な場所で正規の空気圧に戻す必要があります。低空気圧での高速走行はタイヤの損傷を招きます。
ひとことまとめ
スタック脱出の最良の技は、タイヤが「空転」しない限界の力で小刻み揺すりを繰り返すことです。
路面に“足場”を作る方法:砂・板・マット・枝・スノープレートの使い方

タイヤの空転を防ぎ、トラクションを得るため、タイヤの前に足場となる材料(砂、板、マット、スノープレートなど)を敷き詰める方法が有効です。
タイヤと路面(泥や雪道)の間の摩擦係数(滑りにくさ)が低すぎる場合、タイヤの力(トラクション)を路面に伝えることができません。足場材は、この摩擦係数を一時的に高める役割を果たします。
具体的な足場作りと用具
-
砂や小石:
ぬかるみや雪道において、スタックした駆動輪の前方(または後方、小刻み揺すりを行う方向)に、砂、砂利、小石などを撒きます。 -
板やマット:
・車内に車載しているフロアマット、または板切れがあれば、駆動輪の進行方向に対してタイヤに噛みつく角度で敷き込みます。
・スノープレート(=脱出補助用の専用マット)は、この用途のために設計された、最も効果的な道具です。 -
枝葉:
周囲に木の枝や葉がある場合は、これらを敷き詰めるだけでも一時的なトラクションを得られる可能性があります。
注意点
足場材を敷く際は、タイヤが再び空転する前に、低速でゆっくりと発進することが重要です。また、敷いたマットや板が飛び出さないよう、周囲の人や物に注意しましょう。
ひとことまとめ
スタックしたタイヤが路面をつかむ力を高めるため、足場を工夫し、空転させずに脱出を試みましょう。
駆動方式別のコツ:FF/FR/4WD・AWD(電子制御OFF/ONの使い分け)
車の駆動方式(FF:前輪駆動/FR:後輪駆動/4WD・AWD:四輪駆動)ごとに、スタック脱出のためのトラクション回復に適した操作と、電子制御(トラクションコントロールなど)の使い分けがあります。
駆動輪の位置や、システムが空転をどう制御するか(デフロックの有無、電子制御の介入度)によって、最適な脱出方法が異なるためです。特にFF車はエンジンが前輪にかかり、FR車は荷物がないと後輪のトラクションが不足しがちです。
駆動方式別のコツ
| 駆動 | 有効操作 | 避けたい操作 |
|---|---|---|
| FF(前輪駆動) | 小刻み揺すり(後退発進 → 前進の繰り返し)、後輪に重し(トラクション回復のため) | 強い空転(泥や雪を深く掘り下げる) |
| FR(後輪駆動) | 駆動輪に重し、トラクションコントロール一時OFF(わずかな空転でグリップを探す) | 斜め急加速(テールスライドによる危険) |
| 4WD/AWD(四輪駆動) | “スノーモード”・低速ギア、デフロック機能があれば使用(トラクション確保) | ロック状態で高速回転(駆動系損傷の可能性) |
電子制御の利用
最近の車両に搭載されているESCやTCS(トラクションコントロールシステム)は、空転を検知すると出力を絞ってスリップを防ぎますが、スタック時にはこれが逆に脱出を妨げる場合があります。一時的にOFFにすることで、空転を利用して路面を掘る「きっかけ」を作れる場合もありますが、FR車などでは車両挙動が不安定になるため、取扱説明書に従い慎重に行うべきです。
ひとことまとめ
自分の車の駆動方式と車載モード(スノー、ローなど)の特徴を理解し、空転を最小限に抑える運転操作を心がけましょう。
牽引前の準備:牽引ポイントの見分け方・ロープ種類(静的/キネティック)・角度と合図

自力脱出が不可能な場合は、他の車による牽引(=牽引ロープなどで引っ張ること)が必要となります。牽引作業の前には、牽引ポイントの確認、適切な牽引ロープ(ストラップ)の選択、そして牽引方法の合図(コミュニケーション)の確立が必要です。
指定されていない場所に牽引ロープを掛けると、バンパーや車体部品を破損したり、最悪の場合、車体そのものを変形させてしまう危険性があるからです。また、適切なロープと合図があれば、安全でスムーズな牽引が可能です。
牽引前の準備とロープの選択
-
牽引ポイント 車の確認:
・車両の取扱説明書に必ず記載されている、指定の牽引フック(=牽引時にロープを掛けるための金属製のフック)または牽引ポイント(=フックを取り付けるネジ穴など)を使用します。
・バンパーやサスペンション(けん引不可部位)、荷掛けフックなどにロープを掛けるのは絶対にダメです。 -
牽引ロープの種類:
・静的ロープ(=伸びが少ない牽引ロープ):軽いスタックの補助に使用。急な力(ショック)を加えるとロープや車体への負担が大きい。
・キネティックロープ(=ストラップ、衝撃を吸収するために少し伸びる牽引ロープ):深いスタックや泥からの脱出に使用。伸びることでショックを和らげ、慣性力を利用して引く。
・ワイヤー:伸びは無いが丈夫。破断時の跳ね返り(シャックルなど)は非常に危険。 -
角度と合図:
・牽引はできる限り、スタックした車に対して直線で引くのが原則です。牽引角が大きすぎると(45°以上など)、車両の横転や牽引ポイントの破損リスクが高まります。
・ドライバー同士で、ゆっくり引くこと、停止することなどの合図を事前に決めておきましょう。
ひとことまとめ
牽引は必ず取扱説明書記載の牽引ポイントを使用し、牽引ロープは状況に適した伸びを持つものを選び、合図を徹底して安全を確保しましょう。
正しい牽引手順
牽引手順は、「牽引ロープの固定」、「緩み(テンション)の調整」、「ゆっくり引くこと」、そして「安全な解放」の4つのステップを厳守します。
急激な力(ショック)をかけると、ロープやシャックル(=ロープと牽引フックを繋ぐ金具)が破断し、シャックルが弾丸のように飛んで人や車両に当たる重大事故(二次事故)につながる危険があるからです。
正しい牽引手順
-
固定:
・救援車とスタック車の指定された牽引ポイントに牽引ロープを確実に取り付けます。
・シャックルを使用する場合、ネジがしっかり締まっていることを確認し、ロープが絡まないように設置します。 -
テンション(緩み調整):
・ロープにたるみ(緩み)がない状態まで、救援車がゆっくりと前進してテンションを張ります。
・キネティックロープの場合、わずかな伸びを確保することで、ショックを和らげつつ慣性力を伝える準備をします。 -
ゆっくり引く:
・合図を確認した後、救援車は極めてゆっくり(低速ギアで微速前進)牽引を開始し、空転させずに一定の力をかけ続けます。
・スタック車側は、牽引のタイミングに合わせて、空転しない程度に軽くアクセルを踏み、トラクションを補助します。 -
解放と安全:
・スタック車が完全に脱出し、安全な場所まで移動したら停車し、接続時と逆の順序で、シャックルや牽引ロープを外します。
・シャックルや牽引ロープを外す際は、ロープにテンションがかかっていない状態であることを確認し、ロープの反発や跳ね返りに注意します。
ひとことまとめ
牽引時は「ゆっくり引く」を徹底し、シャックルの破断など二次事故の危険から周囲の人を退避させましょう。
してはいけない例:荷掛けフックに牽引、急加速、ホイールスピン連発、ジャッキアップ不安定面

スタック脱出や牽引作業において、車両の破損や人命に関わる重大な事故を避けるため、いくつかの危険な行為を絶対に避ける必要があります。
指定外のフックや構造物に牽引ロープを掛けると、車体やフレームが簡単に曲がってしまうからです。また、空転連発は路面を掘り、状況を悪化させるだけでなく、駆動系への急激な負荷(ショック)を与え、故障(例えば、トランスミッションやデフの損傷)を引き起こします。
絶対にしてはいけない行為
-
指定外の牽引:
荷物固定用の荷掛けフック、サスペンション(車体を支える部品)、またはバンパーなど、取扱説明書でけん引不可部位とされている場所に牽引ロープを掛けること。 -
空転の連発と急加速:
タイヤが埋まっているのにアクセルを強く踏み込み、ホイールスピン連発(空転)させること。これは状況を悪化させるだけでなく、駆動系を損傷させます。 -
ジャッキアップの不安定面:
ぬかるみや雪の上でジャッキアップを行うこと。ジャッキが沈んだり横滑りしたりして車体が落下する危険性があります。 -
高温のクラッチ操作:
マニュアル車で、スタック中に半クラッチ(クラッチを半分だけ繋いだ状態)を多用し、クラッチ(=エンジンとタイヤの間で動力を断続する部品)から焦げた臭い(クラッチの滑りによる摩耗臭)を発生させること。
ひとことまとめ
自力脱出を試みる際は、空転を連発せず、牽引の際は牽引ポイント(牽引フック)以外にロープを掛けないように注意しましょう。
タイヤ・装備の選び方

雪道やぬかるみ走行に備えるためには、車両に合ったタイヤチェーンやスタッドレスタイヤの装着と、いざという時のためのトラクション 回復用具(スノープレートなど)の携行が重要です。
雪や氷の上で安全性を確保するためには、タイヤチェーン(法令で装着が求められる場合がある)や、低温下でグリップ力を保つスタッドレスタイヤが不可欠だからです。また、スタック時のトラクション回復には、物理的にタイヤと路面の間に足場を作る用具(スノープレートなど)が最も効果的です。
雪道・ぬかるみ対策装備
| 装備品 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| タイヤチェーン | 凍結路、深い雪道 | 積載が義務付けられる区間あり。駆動輪に装着。 |
| 牽引ロープ(ストラップ) | スタック時の救援牽引 | キネティック式はショックを和らげ、脱出に有利。 |
| シャックル | 牽引ロープと牽引フックの確実な接続 | ロープの固定に不可欠。 |
| スノープレート/板切れ | トラクション回復のための足場材 | 空転防止。タイヤ前後に敷く。 |
| 安全三角表示板、発炎筒 | 二次事故防止の後方警戒 | 夜間・高速道路では必須。 |
タイヤの選択
雪道や低温下での走行を前提とする場合、スタッドレスタイヤやM+Sマーク(マッド&スノー)の付いたタイヤ(オールテレーンタイヤなど)の使用が推奨されます。
ひとことまとめ
雪道やぬかるみへ向かう際は、タイヤチェーンや牽引ロープ、スノープレートを必ず車載し、万が一のスタックに備えましょう。
EV/HV・SUVの注意点:高電圧に触れない、重量と牽引力、回生ブレーキの挙動

EV(電気自動車)やHV(ハイブリッド車)は高電圧の駆動系統を持っており、スタック時の対応や牽引時には、高電圧部品への接触回避と、回生ブレーキ(=運動エネルギーを電力に変換するシステム)の特有の挙動に注意が必要です。
EV/HV車は、走行用バッテリーに数百ボルトの高電圧電流が流れています。スタックによる車体損傷や牽引時に、高電圧系統(オレンジ色の配線など)に不用意に触れると感電の危険があるためです。また、SUVやミニバンなど車重の大きな車両は、牽引力や空転のリスクも通常車と異なります。
車種別の特殊な注意点
-
EV/HV車と高電圧:
・牽引や脱出作業で高電圧部品に触れるのは絶対ダメです。
・車両に異常(ハイブリッドシステムウォーニングランプの点灯など)がある場合は、すぐにロードサービスに依頼し、高電圧対応の専門家に任せます。
・回生ブレーキ(アクセルオフ時に作動)により、雪道や氷上で意図せず減速しすぎて滑り出す挙動にも注意が必要です。 -
SUV・ミニバン(重量):
車重が重いため、深いぬかるみに沈みやすく、スタックした場合の牽引力は大きくなります。救援車は十分なパワーを持つ車両か、専門のレッカー車を選びます。
ひとことまとめ
EV/HV車は高電圧の危険があるため、スタック時はプロ推奨のロードサービスを最優先で依頼しましょう。
いつプロを呼ぶか
スタックからの脱出は、自力対応に固執せず、勾配が急である、車底が接地している、あるいは夜間や悪天候で安全が確保できない状況下では、迷わずプロのロードサービス依頼に切り替えるべきです。
車底接地(=車の底が路面に乗り上げてタイヤに重さがかかっていない状態)している場合、タイヤにはトラクションが一切かからず、ジャッキアップや牽引による持ち上げ作業が必須となり、一般ドライバーが自力で行うのは困難で危険だからです。また、視界不良は二次事故のリスクが高く、人命が優先されるべきです。
プロ要請の判断早見表
| 状況 | 危険度 | 推奨される行動 |
|---|---|---|
| 車底が完全に乗り上げ(腹がつかえている) | 高 | 即プロ(ロードサービス 依頼)。車体損傷のリスク。 |
| 牽引角が45°以上しか取れない | 中〜高 | プロ。横方向への力が強くなり、牽引ポイント破損の可能性。 |
| 空転を5回以上試みたが改善しない | 中 | プロ。路面を掘り、状況が悪化している。 |
| 氷上、急勾配でのスタック | 高 | プロ。車両が滑り落ちる危険(二次事故)。 |
| 車線内/視界不良・夜間 | 高 | 警察・道路会社に連絡後、ロードサービス 依頼。反射材装着後退避。 |
ロードサービス依頼
JAFや自動車保険付帯のロードサービスに連絡する際は、場所(住所または目印)、路面状況(雪道かぬかるみか)、スタックの深さ、車底の接地状況を正確に伝えましょう。
ひとことまとめ
安全が確保できない、または車底接地している場合は、無理な脱出操作を止め、すぐにロードサービス 依頼をしましょう。
まとめとFAQ:再発防止(空気圧管理・走行ライン・季節準備)+Q1〜Q5

スタックは、不適切な空気圧や、雪道・ぬかるみでの不用意な急加速(空転)が主な原因で発生します。再発防止のためには、季節ごとのタイヤチェックと、慎重な走行が最も有効です。
雪道や寒冷地では、燃料の凍結 や、サイドブレーキのワイヤー凍結、低温によるバッテリー能力低下など、様々なトラブルが発生しやすい環境だからです。事前の準備と、トラクション回復のための基本技術を知っておくことで、トラブルを避けられます。
再発防止のための準備
- 季節の準備:冬季はスタッドレスタイヤまたはタイヤチェーンの携行を必須とし、空気圧を適切に保ちます。
- 空気圧管理:タイヤの空気圧は、路面状況や積載重量に応じて取扱説明書の規定範囲で調整します。
- 走行ライン:雪道やぬかるみでは、轍(わだち)を避け、可能な限り平坦な部分をゆっくり走行するラインを選択します。
- 携行品:牽引ロープ、スノープレート、反射ベストを常時車載しておきましょう。
FAQ(よくある質問)
Q1:スタックしたとき、タイヤを空転させ続けてはいけないのはなぜですか?
A1:タイヤが空転し続けると、泥や雪を深く掘ってしまい、タイヤが埋没して脱出が不可能になるだけでなく、タイヤが熱を持ち周囲の雪を溶かし、氷に変えてしまうからです。また、駆動系(トランスミッションやデフロック部品)に急激な負荷(ショック)がかかり、故障の原因にもなります。
Q2:牽引ポイント車がどこにあるか分かりません。どこを見ればよいですか?
A2:牽引フックや牽引ポイント(シャックル取り付け用のネジ穴など)の位置は、車両の取扱説明書に必ず記載されています。バンパーやサスペンション(車体を支える部品)、荷物固定用のフックなど、けん引不可部位にロープを掛けるのは絶対にダメです。
Q3:空気圧を下げるとスタック 脱出に有利になるのは本当ですか?
A3:ぬかるみや深雪の場合、タイヤの空気圧を通常より10〜20%程度下げることで(取扱説明書の許容範囲内)、タイヤの接地面(路面と触れる部分)が広がり、トラクション回復が期待できます。ただし、脱出後は速やかに正規の空気圧に戻す必要があります。
Q4:雪道やぬかるみで車が沈み、車底が地面に着いてしまいました。どうすれば良いですか?
A4:車底接地(腹がつかえている状態)している場合は、タイヤに荷重がかからず、自力脱出は不可能です。牽引やジャッキアップで車体を持ち上げる作業が必要となるため、プロ推奨のロードサービス依頼(JAFや保険付帯サービスなど)をすぐに行いましょう。
Q5:牽引ロープを繋ぐ際、シャックルを使うと安全だと聞きましたが、注意点はありますか?
A5:シャックルは牽引ロープと牽引フックを強固に繋ぐために使用されますが、キネティックロープなどを使って急激な力を加えた場合、シャックルが破断して飛散する危険があります。牽引手順を守り、作業中は周囲に誰もいないことを確認し、牽引は常にゆっくり引くように心がけてください。
携行品・安全チェックリスト
-
牽引・脱出のための携行品
・牽引ロープまたはキネティックロープ(ストラップ)
・シャックル(牽引用金具、ロープの端に取り付ける場合)
・スノープレートや板切れ(トラクション回復用足場材)
・タイヤチェーン、または滑り止め(雪道の場合)
・懐中電灯またはヘッドライト(夜間用) -
スタック時の安全確認チェックリスト
・ハザードを点灯させましたか?
・安全三角表示板と発炎筒を設置しましたか?
・乗員全員、ガードレール外側など安全な場所へ退避しましたか?
・夜間の場合は反射ベストや反射材を着用しましたか?
・牽引ポイントは取扱説明書で確認しましたか?(バンパーやサスに掛けるのは絶対にダメ)
・空転を連発し、路面を掘り下げていませんか?(掘る前にロードサービス依頼を検討)

最短30分で駆けつけます!
車の故障・パンク・事故車のけん引など、
車のトラブルは「カーレスキュー隊24」に
お任せください。
便利なお支払い方法も充実!
-
現金OK

-
カード払いOK

-
後払い決済OK








