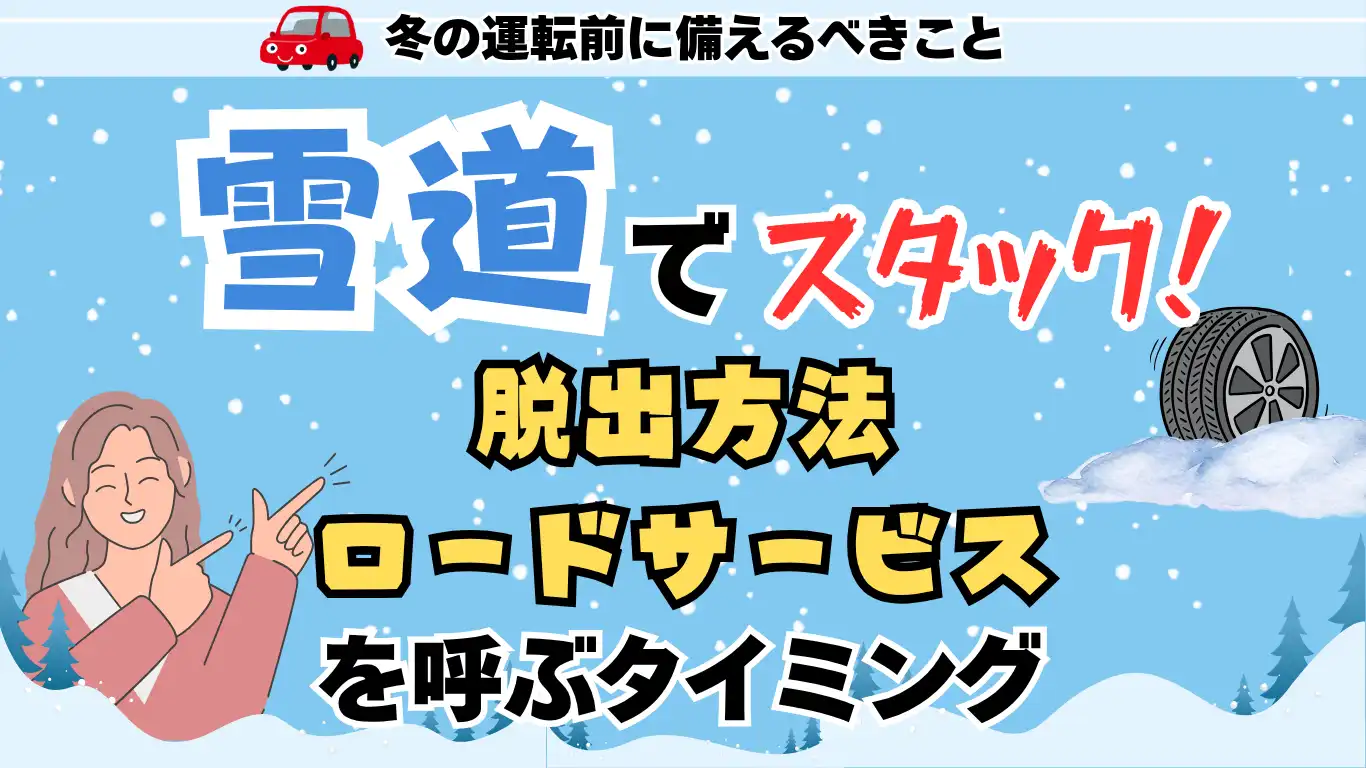
雪国での冬の運転準備をしっかりしていても、突然の積雪道やアイスバーンで車が動かなくなる「スタック」は、誰にでも起こり得るトラブルです。特に人里離れた場所や夜間にスタックしてしまうと、不安と危険が大きく増します。
安全確保 → 状況判断 → “掘らない・滑らせない” → 無理なら早めに救援

焦ってアクセルを踏み込むと、スタックがさらに深くなる
雪道で車が動かなくなったとき、まず人命最優先で安全を確保し、冷静に状況を判断することが成功の鍵です。最もやってはいけないのは、タイヤが空転(滑って回ること)しているのに、さらにアクセルを踏み込み続けることです。
理由:「空転」は地面を掘り、事態を深刻化させる
タイヤが空転し続けると、雪や泥をさらに掘り下げてしまい、タイヤの周囲が氷のように固まって、車底(フロア)が雪に触れてしまう「車底接地」状態に陥ります。
こうなると、自力での脱出は極めて困難となり、プロのロードサービスを呼ばざるを得なくなります。
具体例:判断のフロー
- 安全確保: ハザードを点灯させ、反射ベストを着て、三角表示板や発炎筒で後方警戒を行う(特に視界不良時)。
- 状況診断: どのタイヤが空転しているか、タイヤが埋まっている深さ、雪質、前後に動ける余地があるかを確認します。
- 脱出操作: 空転を避けながら、発進ギア(1速やスノーモード)を使い、小刻みに車を前後に動かす「ゆすり」を試みます。
- 救援要請: 10分程度の試行錯誤で動かなければ、「スタック ロードサービス いつ呼ぶ」という判断基準(後述)に基づき、ロードサービスに連絡します。
雪道スタック脱出は人命最優先で行動し、空転させずにトラクション(タイヤが路面をつかむ力)を回復させるための冷静な対処法を実行しましょう。
初動の安全:停車位置・ハザード・後方表示・乗員退避

周囲の車にスタックを知らせ、自分と乗員は安全な場所に避難する
スタックした場所が交通量の多い道路やカーブの途中である場合、二次事故防止が最優先事項となります。
理由:冬道での視界不良と制動距離の増加
雪道や吹雪道では、視界が悪く、後続車の制動距離(ブレーキが効き始めてから停止するまでの距離)が大幅に伸びます。車内に留まるのは非常に危険です。
- ハザード点灯: すぐにハザードランプを点灯させ、故障を知らせます。
- 乗員退避: 乗員全員、特に子供や高齢者は、反射ベストを着用して、ガードレールの外側など、車から十分に離れた安全な場所に避難します。
- 後方表示: 三角表示板や発炎筒(LEDタイプも含む)を、車の後方に設置し、後方警戒を行います。
具体例:雪に埋もれた発炎筒
発炎筒を雪の上に置くと、雪に埋もれてしまう可能性があります。
もし三角表示板や反射ベストがすぐに取り出せない場合は、車外に出る前に必ずライトなどで自分の存在を周囲に知らせてから、雪道スタック脱出作業に取り掛かってください。
雪道スタック時の安全確保は、二次事故防止と寒さ対策が同時に進行する冬 運転 準備の一部です。
状況診断:どの車輪が沈んだか/雪質(新雪・圧雪・氷)/勾配の有無

スタックの深さと雪質によって脱出方法を変える
雪道スタック脱出を試みる前に、車の状況を正確に把握することが重要です。
理由:誤った判断はスタックを悪化させる
雪質が軽い新雪(パウダースノー)であれば、比較的容易に脱出できる可能性がありますが、溶けた雪が再凍結した氷面や、重い圧雪(締まった雪)の場合は、空転させるとすぐにタイヤが氷を掘ってしまい、手の施しようがなくなります。
- 駆動輪の確認: どの車輪が空転しているか(FF/FR/4WD)。駆動輪が雪を掘っている状況を確認します。
- 勾配の確認: 坂の途中(急勾配)でのスタックは、非常に危険です。脱出に失敗すると、車が滑落するリスクがあります。
- 車底の確認: 車体下部が雪に触れている(車底接地)か確認します。車底接地している場合は、自分での脱出はほぼ不可能です。
具体例:氷面での空転
もし車が氷面や固く締まった圧雪路で空転し始めたら、発進ギアでゆっくりと試すか、滑り止めマットなどの足場づくりにすぐに切り替える必要性があります。
長時間の空転は、タイヤの異常発熱や、駆動系にダメージを与えるリスクもあります。
雪道スタック脱出は、まず状況診断。氷面や車底接地の兆候があれば、すぐにロードサービスいつ呼ぶかの判断に進むべきです。
脱出の基本操作:前後の小刻み揺すり・発進ギア選択・空転を止めるコツ
アクセルは極力やさしく、発進ギア(1速・2速)で「ゆすり」を試す
雪道スタック脱出の基本は、「ゆすり」です。前後に少しずつ動くことで、タイヤの前後に隙間を作り、勢いをつけて脱出を試みます。
理由:空転させずにトラクションを確保する
通常のドライブモードで強いアクセルを踏むと、すぐにタイヤが空転してしまい、トラクション(タイヤが路面をつかむ力)を失います。
- 発進ギアの選択: オートマ車(AT車)の場合は、発進ギア(1速またはスノーモード)を使用します。これにより、エンジンの回転数を低く抑え、タイヤに伝わるトルク(回転力)をやさしくすることができます。
- ゆすりの手順: 1速(またはD)に入れ、ゆっくりアクセルを踏んで前へ少し動く。すぐにブレーキを踏んで止まる。次にR(リバース)に入れ、後ろへ少し動く。これを繰り返すことで、タイヤが埋まった穴を少しずつ広げ、勢いをつけて脱出を試みます。
具体例:電子制御の複雑さと故障
もしスタックから抜け出そうとして、空転を防ぐためのトラクションコントロールシステム(TCS)などが作動しすぎ、かえってエンジン不調(例えば、アイドリング不調やエンスト)を引き起こす場合もあります。
現代の車は電子制御スロットルの不具合やエアフロセンサの特性異常などにより、アイドリングが不安定になったり、エンジンの力不足を感じたりすることがあります。
「ゆすり」は短時間で試み、空転を長引かせないことが重要です。
足場づくり:砂・板・マット・スノープレートの使い方
トラクションを回復させる摩擦材をタイヤの進行方向に差し込む
ゆすりで脱出できない、または氷面で空転している場合は、タイヤがトラクションを得るための足場づくりが必要です。
理由:摩擦力を物理的に増やす
雪や氷は摩擦力が低いため、タイヤの溝に雪が詰まるとさらに滑りやすくなります。タイヤと路面の間に摩擦力の高い物体を差し込むことで、トラクションを回復させます。
- 滑り止めマット/スノープレート: スノープレートや滑り止めマットは、専用の装備品として冬運転準備で携行すべきアイテムです。
- 代用品: 周囲に砂や小石、木の板、または車のフロアマットなどがあれば、代用できます。
具体例:使い方の手順
- 雪を掘る: タイヤの前後の雪を、スコップや手(作業手袋を着用)で少し掘り、タイヤが前に進むための道筋をつけます。
- 差し込み: スノープレートやマットを、空転している駆動輪の進行方向側(前進するならタイヤの前)の、タイヤのすぐ手前に、タイヤの接地面の下に潜り込ませるように正しい差し込み角度で差し込みます。
足場づくりは、空転で掘ってしまった溝を埋め、トラクションを取り戻すための物理的な対処法です。
タイヤ装備の使い分け:チェーン/スタッドレス/オールテレーンの違い

冬運転準備で最も重要なのは、雪道に適したタイヤ装備
スタックを予防するため、またスタック時の脱出を容易にするため、タイヤの装備について理解しておく必要性があります。
理由:路面状況に応じてグリップ力(つかむ力)が異なる
- スタッドレスタイヤ: 圧雪やシャーベット状の雪上での走行に優れています。特殊なゴムが低温でも柔らかさを保ち、雪を掴んで走ります。しかし、凍結路面(氷面)では制動距離が長くなる傾向があるため、過信は禁物です。
- タイヤチェーン: 新雪や凍結した急勾配での登坂に最大のグリップ力を発揮します。装着が面倒ですが、規制区間では必須となります。
- オールテレーンタイヤ: 浅雪や泥といった悪路には適していますが、深い雪や氷面ではスタッドレスやチェーンに比べてトラクションは劣ります。
具体例:装着義務と規制
タイヤチェーン付け方は事前の練習が不可欠です。近年は、特定の雪道区間においてチェーンの装着が義務付けられるタイヤチェーン規制が実施されることがあるため、冬運転準備として適合するチェーンを携行し、付け方を習得しておく必要性があります。
冬運転準備として、スタッドレスだけでも十分な場合が多いですが、チェーンの携行と付け方の習得は、安全対策上必須の準備です。
タイヤ装備の適性比較
(以下の数値や情報は、一般的な推奨事項や情報に基づくものです。)
| 装備 | 適する路面 | 速度目安 | 着脱性 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| スタッドレス | 圧雪・シャーベット | 通常域 | 高 | 凍結面は制動距離長い |
| チェーン | 新雪・凍結・登坂 | 低速 | 中 | クリアランス・規制遵守 |
| オールテレーン | 浅雪・悪路 | 通常域 | 高 | 深雪・氷は弱い |
牽引の前準備:牽引ポイントの見分け方・ロープ種類・合図と角度

牽引は牽引フックにキネティックロープを使い、角度を意識する
自分での脱出操作や足場づくりでスタックが解決しない場合、他車による牽引(引っ張って動かすこと)が最終手段となります。
理由:非指定箇所への牽引は車体破損の原因
牽引作業で最も注意点が必要なのは、ロープをかける場所です。
牽引フック(牽引ポイント)は、必ず車の取扱説明書で指定された箇所を使用してください。
非指定箇所(バンパー、サスペンションの一部など)にロープをかけると、車体が破損したり、ロープが外れたりして重大な二次事故につながる危険性があります。
牽引ロープの種類
- 静的ロープ: 伸び縮みしないため、引っ張る際に衝撃が大きくなりがちです。
- キネティックロープ(少し伸びて引く力をやわらげる牽引ロープ): 引っ張る際の衝撃を吸収し、車体やロープへの負荷を軽減します。スタック脱出時の牽引に適しています。
具体例:牽引時の角度
牽引を行う際は、牽引フックに装着した牽引ロープが、牽引する方向に対して角度がつきすぎないように注意します。
角度が大きすぎると、フックや車体に不必要な横方向の力がかかり、破損の原因となります。
牽引は必ず牽引フックを使用し、衝撃を抑えるキネティックロープと、角度の確認が前準備の最重要注意点です。
正しい牽引手順とNG例

急な力は絶対ダメ。優しく、ゆっくりと牽引を開始する
牽引は、脱出させる車と牽引する車(救援車)の連携が最も重要です。
理由:駆動系や牽引フックの保護
急激にロープを引っ張ると、ロープや牽引フックに大きな負担がかかるだけでなく、最悪の場合、車体の牽引ポイントが破損したり、エンジンやミッションといった駆動系にダメージを与えたりする危険性があります。
- 正しい手順: ロープを張り、牽引する側がゆっくりと発進ギアで進み始め、徐々に力を加えてスタック車を動かします。
- NG例: 牽引フックではない荷掛けフック(荷物を固定するためのフック)などにロープをかけるのは絶対ダメです。また、ロープがたるんだ状態から急激に引っ張るのも絶対ダメです。
具体例:電子制御の故障と牽引
もしスタック中に車が走行不能となり、エンジンの故障コード(例:O2センサのヒーター断線や、エアフロセンサの特性異常、またはエンジンECUの不良)が検出されていた場合、牽引によって事態が悪化する可能性も考慮し、プロのロードサービスに依頼する方が賢明です。
牽引手順の最重要注意点は、急な動作を避け、ロープにテンションがかかった状態でゆっくり引くことです。
いつプロを呼ぶか

自分での脱出に危険度が高まる、または30分以上スタックが解消しない場合は、迷わず救援を要請する
雪道スタック脱出を試みる際は、無理は禁物です。人命最優先の観点から、スタックロードサービスいつ呼ぶかの判断基準を知っておきましょう。
理由:プロの装備と技術は二次事故を回避する
プロのロードサービスは、雪道用の特殊なレッカー装備や、牽引の専門的な使い方を知っています。
- 車底接地: 車底が雪に乗り上げてタイヤが浮いている状態は、タイヤに荷重(重さ)がかからないため、トラクションを得られず、自力脱出は不可能です。
- 急勾配・氷面: 坂道や氷面では、脱出作業中に車が滑落する危険度が極めて高いです。
- 視界不良・夜間: 視界が悪い状況や夜間の路肩での作業は、二次事故のリスクが高まるため、道路会社・警察またはロードサービスの指示に従い、路上作業を避けるべきです。
具体例:故障とスタックの複合
スタックした際に、無理な運転を続けた結果、エンジンチェックランプが点灯したり、エンジン不調(エンストやハンチング)が発生したりする場合があります。
この場合、単なるスタック脱出だけでなく、複雑な電子制御の故障修理も必要となるため、すぐにプロを呼ぶべきです。
車底接地や急勾配、氷面など、危険度が高い状況では、スタックロードサービスいつ呼ぶかの判断を早めに行い、人命最優先で救援を待機してください。
プロ要請の判断基準(例)
(以下の数値や内容は、一般的な判断基準に基づくものです。)
| 状況 | 危険度 | 推奨 |
|---|---|---|
| 車底が乗り上げ(フロア接地) | 高 | 即プロ |
| 傾斜10%超+氷面 | 高 | 即プロ |
| 牽引角が取れない(45°以上) | 中〜高 | プロ |
| 視界不良・夜間・路肩狭い | 高 | 道路会社・警察 |
待ち時間の作法:寒さ対策・燃料・排気ガス逆流防止・位置情報共有
寒さ対策を万全にし、排気ガスが車内に入らないよう注意点を徹底する
ロードサービスの到着目安を待つ間、特に極寒の環境では、寒さ対策と排気ガスによる中毒の注意点が命に関わります。
理由:低体温症と一酸化炭素中毒の危険性
スタックしたからといって、エンジンを切りっぱなしにすると、車内が冷え込み低体温症のリスクがあります。暖房を使うためにエンジンをかけている場合、排気ガスが車内に入り込む危険性があります。
- 排気ガス逆流防止: 大雪でマフラーの排気口が雪に埋まってしまうと、排気ガスが車内に逆流する危険性があります。時々窓を開けて換気を行うか、マフラー周辺の雪をこまめに除雪し、排気口を塞がないように注意点を徹底してください。
- 燃料管理: エンジンをかけっぱなしにする場合は、燃料(ガソリン)が切れないよう、残量に注意します。冬運転準備として、常にガソリン残量を多めにしておく必要性があります。
- 位置情報共有: 待機中は、ロードサービスに対して正確な位置情報共有を維持し、到着目安を確認しましょう。
具体例:排気口の詰まり
マフラー内に水が凍結したり、雪が詰まったりすることで、エンジンの回転が上がらなくなったり、エンジンがかからない(エンスト)状態になったりする事例もあります。
このような場合、サービスカーの救援を待つ間に、マフラーのテールパイプを叩いたり、棒などを差し込んで詰まりを解消させたりする対処法が有効な場合もあります。
待機中は、寒さ対策と排気ガス逆流防止の注意点を徹底し、人命最優先で救援を待ちましょう。
車種別の注意:FF/FR/4WD・AWD、EV・HV(高電圧に触れない)
駆動方式でスタック脱出の特性が異なり、HV・EVは電気系に注意点が多い
車の駆動方式(FF:前輪駆動、FR:後輪駆動、4WD:四輪駆動)によって、スタック時の対処法や牽引の手順が変わります。
理由:電子制御の複雑さと高電圧の危険性
- FF/FR/4WD: FFは比較的雪道に強く、FRは滑りやすい傾向があります。4WD(四輪駆動)は、トラクションを確保しやすいですが、スタックすると四輪とも埋まってしまい、脱出が難しくなる場合があります。
- EV/HV: ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)は、複雑な電子制御システムを持っています。ハイブリッドシステムウォーニングランプの点灯 など、故障が起きた場合は自力脱出は諦め、プロを呼ぶべきです。
- 高電圧への注意点: EVやHVは高電圧の駆動用バッテリーを使用しており、高電圧配線(オレンジ色が多い)や関連ユニットには絶対に触れないでください。牽引や脱出作業時も、12Vの補機バッテリー周辺以外には手を出さないことが安全上の最重要注意点です。
具体例:電子制御の故障
HVで故障コード「P3130-346」(インバータ冷却系統異常)が検出された事例では、ウォーターポンプの不良が原因でした。
また、ABSの警告ランプ点灯の原因がコネクタ部分の青錆による接触不良であった事例もあり、冬季の湿度や融雪剤の影響で電子制御系のトラブルが起こりうる可能性があります。
駆動方式を理解し、特にEV/HV車は、高電圧システム周辺には触れず、安全を確保してロードサービスの到着を待ってください。
冬の事前準備リスト

スタックしないための運転 準備と常備品の確認を徹底する
雪道スタックは、事前の準備と整備で回避できる可能性が高まります。冬運転準備は、タイヤ装備だけでなく、車載常備品も重要です。
理由:予防整備は故障リスクを減らす
- 日常の点検: エンジンオイルの劣化(高温時の酸化や排気ガスの混入によるスラッジ生成)は、オイルコントロールバルブの詰まりやエンジン不調の原因となり、冬季のエンジン始動不良につながる可能性があります。定期的なオイル交換や点検は冬運転準備に不可欠です。
- タイヤ空気圧: 空気圧が適正でないと、雪道でのトラクションが低下し、スタックしやすくなります。
- 常備品: 牽引ロープ、スコップ、滑り止めマット、毛布など、脱出や待機に必要な装備品を積んでおきましょう。
具体例:整備不良と故障
エンジンをかけてもエンストする症状は、フューエルポンプの不良や電子制御スロットルボディの不良など、複雑な故障が原因の場合が多いため、冬季に入る前に整備工場での点検が強く推奨されます。
冬の事前準備リストを活用し、装備と整備を徹底することで、雪道でのスタックリスクを最小限に抑えましょう。
冬の事前準備チェック
(以下の内容は、一般的な推奨事項に基づいて記載しています。)
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| チェーン(適合サイズ・試装着) | 軍手・膝当て付き |
| 牽引ロープ・シャックル | 取説でフック位置確認 |
| 滑り止めマット・スコップ | 折りたたみ可 |
| 毛布・カイロ・水・軽食 | 低体温防止 |
| 反射ベスト・ライト | 見つけてもらう工夫 |
| モバイルバッテリー | 連絡維持 |
| ガソリン残量(常に多め) | 渋滞対策・暖房用 |
まとめ&FAQ:再発防止(空気圧・積載・走行ライン)+Q1〜Q5
雪道スタック脱出は空転を防ぎ、無理をしないことが鉄則
雪道でのスタックから脱出する対処法は、「安全確保」と「空転を長引かせない」ことがすべてです。
自分での脱出が難しいと判断したら、ロードサービスいつ呼ぶかの判断を遅らせず、早めにプロの救援を仰ぐことで、二次事故や車の故障を防ぐことができます。
再発防止策
- 適正な空気圧: 低すぎるとスタックしやすいですが、高すぎても接地面が減り滑りやすくなります。車種指定の空気圧を守りましょう。
- 急な操作を避ける: 雪道では急ハンドル、急ブレーキ、急加速(空転の原因)を避けて運転することが、スタック防止に最も重要です。
よくある質問(Q1〜Q5)
Q1:スタックした時、タイヤの空気圧を少し下げた方が脱出しやすいですか?
A:一般論として、空気圧を意図的に下げることで、タイヤの接地面を広げ、トラクション(路面をつかむ力)を増す対処法が試みられることがありますが、これはタイヤのサイドウォールに大きな負担をかけ、破損のリスクを伴います。自分で安易に行うのではなく、スノープレートや滑り止めマットなどの装備を優先的に使用する方が安全です。
Q2:スタック時、発進ギア(1速や2速)でゆっくり進む方法を教えてください。
A:オートマ車の場合、D(ドライブ)に入れると2速発進になることがありますが、雪上では1速や2速(ローギア)を意図的に選択できる発進ギア(スノーモードなど)があれば利用します。最も重要な手順は、空転が始まった瞬間にアクセルを戻すことです。ゆっくり発進ギアでタイヤをわずかに動かし、空転を止める操作を繰り返す「ゆすり」で脱出を試みます。
Q3:牽引してもらうとき、ロープは車のどこにかけても大丈夫ですか?
A:絶対ダメです。牽引は、必ず車の取扱説明書で指定された牽引ポイント(牽引フック)のみを使用してください。荷掛けフックやサスペンションの一部など、指定外の場所にロープをかけると、車体や駆動系に重大な破損を引き起こす危険性があります。
Q4:スタック中にエンジンチェックランプが点灯しました。どうすればいいですか?
A:エンジンチェックランプの点灯は、O2センサの断線や、エアフロセンサの特性異常、カム角センサの不良など、電子制御系の複雑な故障を示しています。自分での対処法は不可能であり、無理に脱出を試みると故障を悪化させる危険度が高まります。人命最優先で安全な場所に避難し、ロードサービスを呼んでください。
Q5:HV車が雪道でスタックした場合、高電圧バッテリーに注意点はありますか?
A:HV車は駆動用の高電圧バッテリー(一般的にオレンジ色の配線)を搭載しています。牽引や脱出作業で車体下部やエンジンルームを扱う際、高電圧系統には絶対に触れないように注意点を徹底してください。スタックにより車体が傾いたり、破損したりした場合、高電圧システムに異常が発生する危険性があります。
携行品&安全チェックリスト
| 分類 | 必携品 | 備考 |
|---|---|---|
| 脱出装備 | 牽引ロープ・シャックル | 取説でフック位置確認 |
| 滑り止めマット・スコップ | スノープレートも推奨 | |
| タイヤチェーン(適合サイズ) | 付け方を習得しておく | |
| 安全確保 | 反射ベスト・三角表示板 | 視界不良時に必須 |
| 発炎筒(またはLEDライト) | 後方警戒用 | |
| 待機・寒さ対策 | 毛布・カイロ・水・軽食 | 低体温防止 |
| モバイルバッテリー | 連絡維持 | |
| ガソリン残量 | 常に半分以上を推奨 |
安全・法令 再確認
- 人命最優先。車外退避・後方警戒・反射材の活用を徹底。
- 雪道、視界不良、氷面では無理をせず、道路会社・警察・ロードサービスの指示に従う。
- 空転は絶対ダメ。牽引フック以外に牽引ロープを掛けない。

最短30分で駆けつけます!
車の故障・パンク・事故車のけん引など、
車のトラブルは「カーレスキュー隊24」に
お任せください。
便利なお支払い方法も充実!
-
現金OK

-
カード払いOK

-
後払い決済OK








