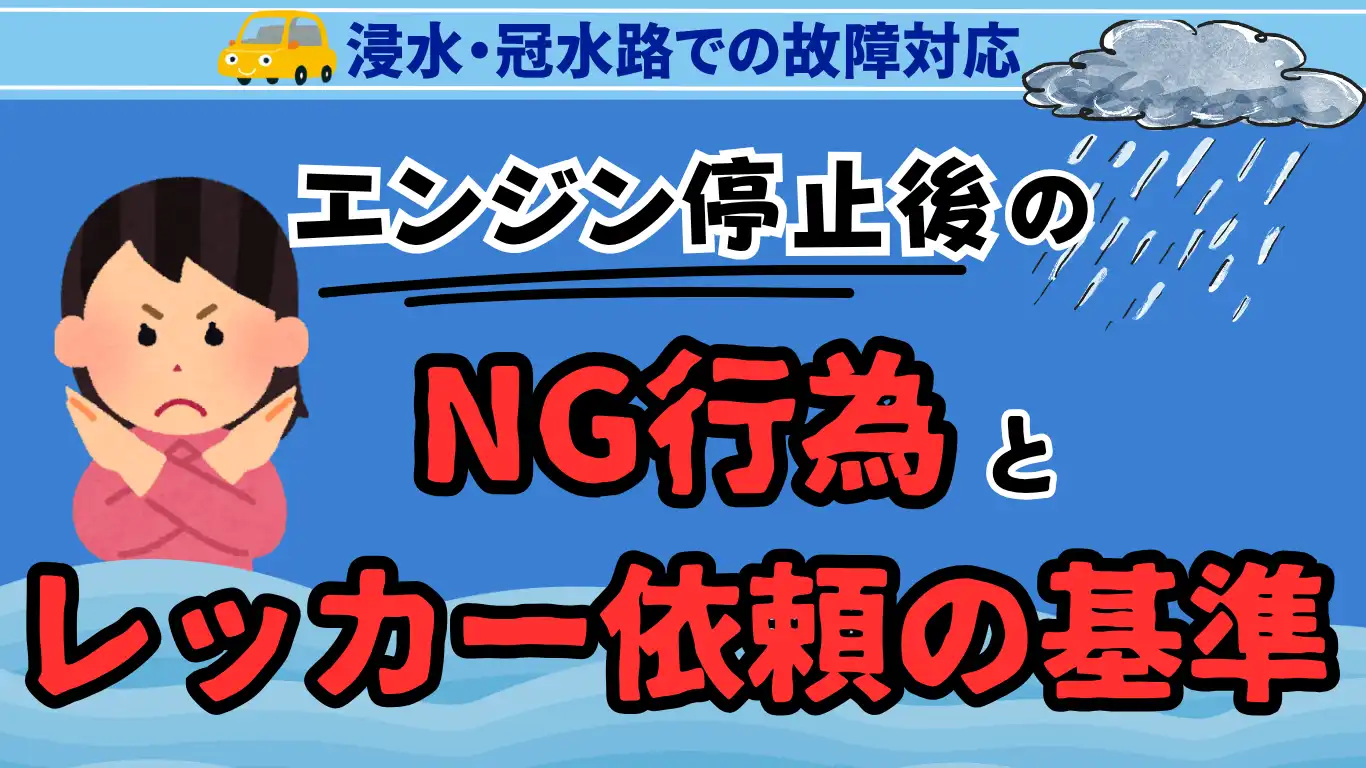
ゲリラ豪雨や台風などによる浸水や冠水は、車にとって最も深刻な故障の原因となります。特に、冠水した道路を走行中にエンジン停止してしまった場合、その後の対処法が車の命運を分けます。
水没車対応の鉄則は、「絶対にエンジンを再始動しない」ことです。この記事では、浸水や冠水に見舞われた際、人命最優先で安全を確保し、車の被害を最小限に抑えるための初動と、プロのロードサービスをレッカー依頼基準に基づいていつ呼ぶべきかという全手順を、詳しく解説します。
水に浸かったら再始動しない。安全退避 → 通報 → 搬送が原則

ポイント一言:浸水故障エンジン停止したら、エンジン再始動NGが鉄則
冠水した道路で車がエンジン停止してしまった場合、水没車対応の最も重要な手順は、安全を確保した後、絶対にエンジンを再始動しないことです。
理由:再始動は修理不可能な致命傷を負わせる行為
エンジンが水を吸い込んで止まった状態(ハイドロロック)で無理に再始動を試みると、エンジン内部のピストンやコンロッドといった部品が曲がったり折れたりする致命的な故障につながります。水による故障の場合、自力で対応することは考えず、レッカー依頼基準に従ってプロに連絡し、搬送を待つのが原則です。
具体例:ハイドロロックのリスク
ハイドロロック(水が入ってエンジンが動かなくなること)が発生すると、エンジン自体を丸ごと交換するほどの高額な修理費用が発生します。特に水かさが増している状況では、人命最優先で車から離れ、救援を待つのが最善の対処法です。
まとめ
冠水車対応は、「再始動NG」を徹底し、安全に退避したら、速やかにレッカーを手配してください。
なぜ再始動NGか:ハイドロロック・ショート・二次被害の仕組み

ポイント一言:水はエンジンと電装系を同時に破壊する
浸水故障が深刻化するのは、水がエンジンだけでなく、車の「頭脳」である電装系にも広範な二次被害をもたらすためです。
理由:水は圧縮できず、電気を導く
- ハイドロロック(水による致命傷): エンジンは、吸気口(空気を吸い込む場所)から水が入り込むと、燃焼室に水が溜まります。水はガソリンのように圧縮できないため、ピストンが水にぶつかって止まり、エンジン内部の部品が破損します。
- 電装系のショート: 車にはECU(車のコンピューター)や多数のセンサー、配線が張り巡らされています。水に浸かると、配線やコネクタ部でショート(短絡)が発生し、ECUやセンサー類が破壊される二次被害が発生します。
- 錆による長期的な不具合: オルタネーター(発電機)やAT・CVT(変速機)、ブレーキ系統の部品が水に濡れると、内部に水が残り、後で錆が発生して故障を引き起こすリスクが高まります。
具体例:ECUとセンサー類の故障
水濡れによるショートや腐食は、エンジン制御に直結するECU(エンジン制御コンピューター)や各種センサーに故障を引き起こします。例えば、O2センサーヒーターの断線(P0155など)や、エアフロセンサの特性異常、スロットルボディのカーボン詰まりなどは、エンジンチェックランプ点灯やエンスト(P1603など)の原因となりますが、浸水はこれらの電子部品の故障リスクを大幅に高めます。
まとめ
エンジン再始動NGを徹底することで、最も高額な修理が必要となるハイドロロックと、電装系の広範なショートによる二次被害を防ぎます。
初動の安全:停車位置・ハザード・後方表示・乗員退避
ポイント一言:人命最優先で車外へ。水没を避けるため高台へ避難する
冠水路を走行中にエンジン停止したら、まず人命最優先で安全を確保します。水位が急激に上昇する可能性もあるため、退避の手順は迅速に行う必要があります。
理由:水流は車を流し、水位上昇は命を脅かす
冠水時には、見えない場所が深く掘られていたり、マンホールが開いていたりする危険があります。
- 停車:可能であれば、高台や路肩など、水没が浅い場所に停車させます。
- 退避:ハザードを点灯させ、三角表示板や発炎筒(後方表示)の準備を安全な場所から行います。
- 避難:乗員全員が車外へ出て、すぐに冠水していない安全な場所に退避します。
具体例:高速道路での水没
高速道路で冠水が発生した場合、路肩に停車後、ガードレール外など車から離れた場所へ避難することが必須です。
まとめ
初動の安全は、「冠水域からの脱出」と「後方表示」です。
その場で絶対にしないこと:セル連打・押し掛け・ジャッキアップ・ドア全開放置など

ポイント一言:エンジン再始動NGを基本に、浸水被害を拡大させる行為は絶対ダメ
浸水した車に対しては、故障の原因を悪化させ、修理費用を不必要に高めるNG行為が多数あります。
理由:ハイドロロックと電装系ショートの回避
- セル連打(再始動NG): 最も絶対ダメな行為です。エンジン内部に水が入っている状態でセルモーターを回し続ける(セル連打)と、ハイドロロックを引き起こし、エンジンが破壊されます。
- 押し掛け: エンジンが止まった車を人力で押して再始動させる方法も、ハイドロロックのリスクがあるため絶対ダメです。
- ジャッキアップ: 濡れた地面でジャッキアップを試みると、車体が不安定になり、人命に関わる二次被害のリスクがあります。
- ドア全開放置: 室内が浸水している場合、ドア全開放置はさらなる水の侵入を許し、電装品や内装(シート、カーペット)の汚損を広げます。ECUやヒューズボックスなど、電装系の部品は床上に配置されていることが多いです。
具体例:ECUやCVTの被害
ECUやAT・CVTといった複雑な電装品が水没した場合、G-scanなどのスキャンツールによる故障コードの診断が必要となります。水没したAT・CVTは、内部チェーンの切れや変速不良(ステップモーターの不良)といった深刻な故障を引き起こす可能性があり、再始動を試みることで、さらに電装系故障の二次被害が広がる危険性があります。
まとめ
浸水車両は「触らない」「回さない」を徹底し、レッカー依頼基準に基づいてプロの対応を待ちましょう。
水位と時間の目安:床下/床上/ボンネット上の被害イメージ
ポイント一言:床上浸水(フロア侵入)したら、電装と内装に甚大な被害
水没車対応では、浸水レベルに応じて、車が受けた故障の深刻度と、レッカー依頼基準が変わってきます。
理由:水位が上がるほど、電装系故障とエンジン損傷のリスクが高まる
車体の下部には、排気管、ブレーキ系統、牽引フック、そして駆動系(AT・CVT)のセンサーや配線の一部が配置されています。
- 床下浸水: タイヤの下部からハブ(車輪の軸)程度の浅い水たまりでは、主にブレーキ性能の低下、オルタネーター(発電機)などの電装系への軽微な影響が考えられます。
- 床上浸水(フロア侵入): 車内に水が侵入し始めたレベルです。この水位に達すると、ECU(車のコンピューター)やヒューズボックス、電装系ハーネス(配線)のコネクタが水に浸かり、ショートや汚損が発生し、走行不能となるリスクが急増します。内装の交換、消毒・消臭が必要となります。
- ボンネット上浸水: 吸気口や排気口が完全に水没するレベルです。エンジン内部に水が侵入し、ハイドロロックを起こす危険性が極めて高いです。
具体例:ECUと電装系の故障コード
ECUは車のエンジン制御を司るため、床上浸水でECUが汚損すると、エンジンの始動不良(フューエルポンプAssy不良による始動不良など)やアイドリング不調(電子制御スロットルボディの不良など)を引き起こす可能性があります。
まとめ
浸水レベルが「床上」に達したら、電装系の致命的な故障が確定するため、再始動NGを徹底し、即座にレッカーを手配してください。
浸水レベル別リスク(一般目安)
| レベル | 状況 | 主なリスク | 現場対応 |
|---|---|---|---|
| 床下(タイヤ下部〜ハブ) | 浅い水たまり | ブレーキ低下・電装濡れ | 停車 → 退避 → 搬送検討 |
| 床上(フロア侵入) | 室内に水 | 配線・内装・ECU汚損 | 再始動NG → 積載搬送 |
| ボンネット上(吸気口以上) | 深い冠水 | エンジン致命傷・高電圧危険 | 接近禁止 → 通報 → 積載搬送 |
EV・HVの注意:高電圧部に近づかない・水没時は距離を取る・12V管理のみ
ポイント一言:EV・HVの水没車対応は感電リスクがあるため特に危険
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)は、冠水による電装系故障リスクがガソリン車よりも高くなります。
理由:高電圧バッテリーの感電リスク
EV・HVは、駆動用の高電圧バッテリーを搭載しています。水没により高電圧系統の配線やユニットが損傷すると、感電の危険が伴います。
- 高電圧システムへの注意: 高電圧配線は一般的にオレンジ色で識別されています。水没している場合は、絶対に触れないでください。
- 12V管理: EV・HVも通常の12Vの補機バッテリー(バッテリー上がり時にジャンピングスタートで使用するバッテリー)を搭載しており、電装品の制御に使われています。しかし、水没時や冠水時は、12V系統であってもショートのリスクがあるため、自力でヒューズやバッテリーに触れる対処法は避けるべきです。
具体例:HVの冷却故障
ハイブリッド車では、インバータ冷却系統の異常(P3130-346など)がウォーターポンプの不良で発生する事例があります。冠水や浸水は、これらの冷却系統にも影響を及ぼす危険性があります。
まとめ
EV・HVが水没した場合は、高電圧による感電リスクがあるため、人命最優先で車から距離を取り、ロードサービスに高電圧車である旨を伝えて積載搬送を依頼してください。
牽引・レッカー基準

ポイント一言:床上浸水またはCVT不動は積載車(車両を完全に載せて運ぶ車)を依頼する
水没車対応のレッカー依頼基準は、車への二次被害を防ぐため、牽引(タイヤを接地させて引っ張る方法)ではなく、積載車による搬送が原則となります。
理由:駆動系故障と電装系のショート防止
- 積載車(積載車推奨ケース): 床上浸水した車は、ECUやAT・CVTに浸水故障を抱えている可能性が高く、牽引により駆動系に負担をかけるのは絶対ダメです。特にEV・HV車は、高電圧システム保護のため、積載車が唯一推奨されます。
- ドーリー(ドーリー必要条件): AT・CVTが故障(走行不能)していてタイヤが回らない車を牽引する場合、動かない車輪を台車に乗せて運ぶドーリーが必要となる場合があります。
- 短距離移動: レッカーが到着する前に安全な場所へ短距離移動させる必要がある場合は、AT・CVTが不動でなければ低速で牽引を検討できますが、高速道路や交通量が多い場所では絶対ダメです。
具体例:CVTの故障
CVT(無段変速機)が水没した場合、CVT内部チェーンの切れやステップモーターの不良による変速不良、さらにはセンサーの断線など、複数の故障リスクがあります。これらの場合、タイヤを浮かせた積載車による搬送が必須です。
まとめ
水没車対応は、床上浸水やEV・HV車の場合、積載車推奨ケースに該当します。牽引による二次被害を防ぎましょう。
牽引・搬送の早見表(一般論)
| 状況 | 積載車 | ホイールリフト | ドーリー |
|---|---|---|---|
| 床上浸水 | ◎推奨 | △短距離のみ | ○状況次第 |
| AT/CVT不動 | ◎ | △ | ○ |
| EV/HV水没疑い | ◎唯一推奨 | × | × |
通報と位置共有:非常電話・スマホ・キロポスト・地図リンクの伝え方

ポイント一言:水没時は車名に加え、浸水レベルと再始動NGを明確に伝える
冠水時にロードサービスを呼ぶ際、状況を正確に伝えることで、レッカー隊員は適切な装備(積載車など)と到着目安を予測できます。
理由:特殊な対応には詳細な情報が必要
通常のバッテリー上がりやパンクとは異なり、冠水はハイドロロックやショートのリスクを伴います。
- 伝えるべき情報: 「冠水路でエンジン停止した」「再始動は試みていない」「床上浸水している」など、水没車対応に必要な情報を具体的に伝えます。
- 位置情報: 高速道路上であれば、非常電話を利用するか、キロポスト(高速道路の距離表示)の数字を伝えます。一般道であれば、住所や目標物を伝えます。
具体例:通話テンプレの活用
通話テンプレを活用し、人命最優先で退避が完了している旨をまず伝えましょう。
まとめ
通報時は、「浸水故障エンジン停止」の事実と、「再始動NG」の対応をしている旨を明確に伝えましょう。
通話テンプレ
| 項目 | 話す内容例 |
|---|---|
| 場所 | 〇〇高速道路・上下線・キロポスト〇〇キロ付近/一般道の目印 |
| 状況 | 冠水で停止し、再始動は絶対ダメなので試していません。床上浸水の目安です。 |
| 車両 | 色・車名・年式・2WD/4WD・EV/HVの有無 |
| 安全措置 | 退避・表示板・発炎筒の有無 |
| 希望 | 搬送先住所/積載車の依頼と到着目安/支払い方法 |
到着までの待機:風下待機・低体温対策・排気逆流防止・持ち物
ポイント一言:安全な場所で低体温対策を万全にする
冠水時は天候が荒れていることが多く、ロードサービスの到着までの待機中に体調を崩さないよう注意が必要です。
理由:悪天候による低体温と二次被害のリスク
- 避難位置: 水没車からは離れ、風向き(風下)に注意しながら、雨風がしのげる安全な場所で待機します。
- 低体温対策: 濡れた衣類はすぐに着替え、毛布やカイロなどで体温を保ちます。
- 持ち物: 待機時間が長引く場合に備え、携帯電話(位置共有用)、モバイルバッテリー、飲料水などを事前に常備品として用意しておきましょう。
- 排気逆流防止: 浸水によって排気管が詰まる(または水没している)状況は、排気ガス逆流防止の注意が必要ですが、エンジンをかけていない状態であればこのリスクは発生しません。
具体例:待機中の電装系トラブル
水没後、ヒューズや電装系に水が浸入し、バッテリーがショートを起こし発火するリスクも否定できません。安全のため、車から距離を取ることが最も重要です。
まとめ
到着までの待機は、「車に近づかない」ことと「低体温対策」を徹底しましょう。
搬送先の選び方:ディーラー/電装系が強い工場/消毒・乾燥メニュー

ポイント一言:水没車対応に慣れた搬送先と、電装系整備ができる工場を選ぶ
浸水故障を経験した車は、エンジンのオーバーホールだけでなく、電装系、内装の広範な点検が必要です。
理由:ECUやハーネスの点検が必要
- ディーラー: 車種特有のECU(車のコンピューター)やハーネス(配線)に関する故障コード(P0171などのリーンの異常や、O2センサーの断線など)の診断や、ハイブリッドシステムの特殊な対応(リニア弁オフセット学習手順など)が必要な場合に適しています。
- 電装系が強い工場: 電装系のショートやオルタネーター、ヒューズボックス、ワイヤーハーネスの断線など、電装品の故障対応に慣れています。
- 内装・消毒: 床上浸水があった場合、カビや悪臭を防ぐために、シートやカーペットを外し、徹底した消毒・乾燥メニューを実施できる工場を選ぶ必要があります。
具体例:ECUの故障
エンジンECUの不良や故障は、エンジンチェックランプ点灯やエンスト(P1603,P1605など)、アイドリング不調、さらには初爆後のエンストなど、様々な症状を引き起こします。浸水はECUのショートリスクを飛躍的に高めるため、搬送先は電装系の修理実績を確認しましょう。
まとめ
水没車対応を依頼する際は、電装系の故障を見越した搬送先と、消毒・乾燥メニューの有無を確認しましょう。
費用と時間の目安
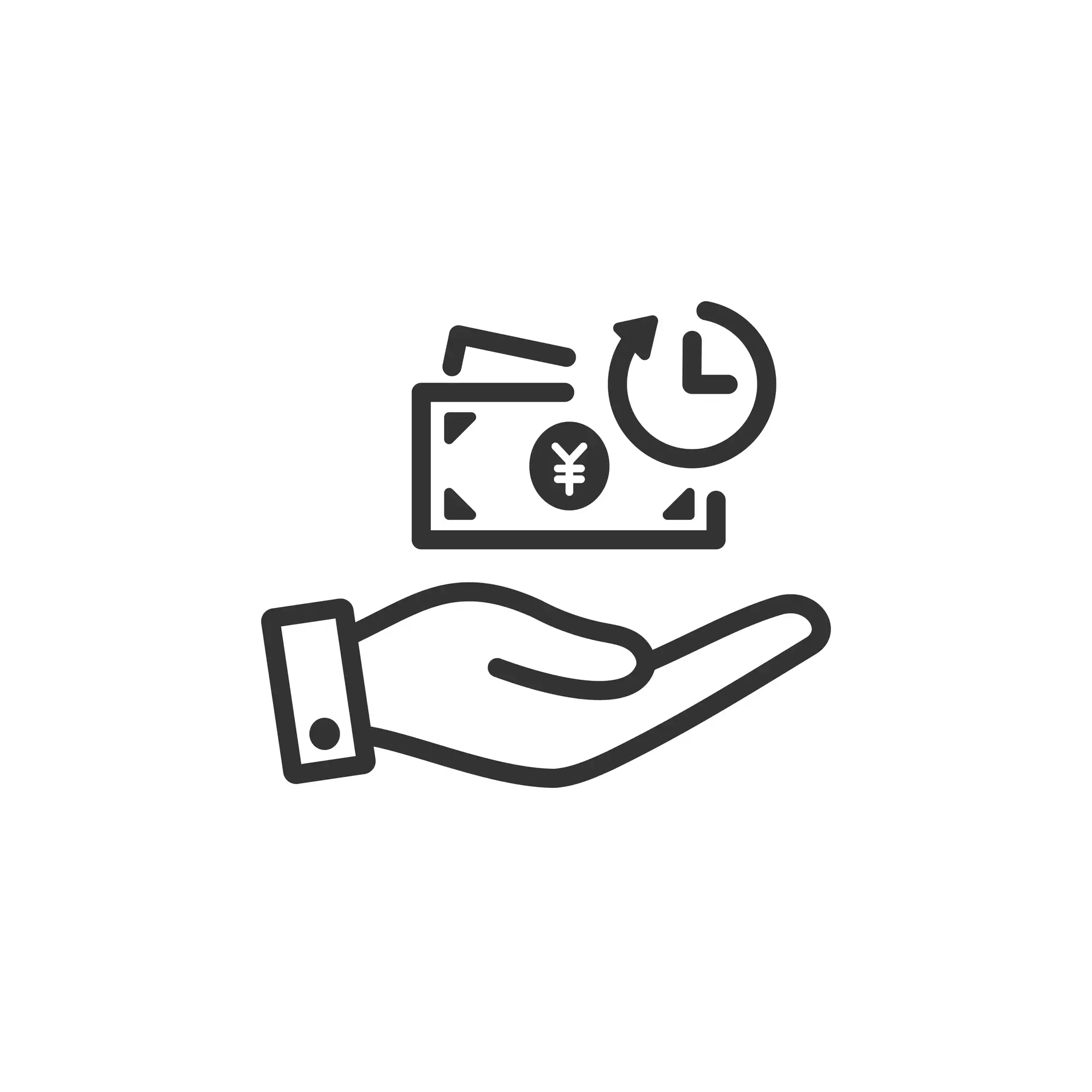
ポイント一言:レッカー費用は回送距離と夜間割増で大きく変動する
冠水による故障の場合、レッカー(回送=レッカーで車を運ぶこと)による搬送が必須です。費用と時間は、通常の故障よりも特殊な対応が必要となるため、到着目安と共に料金を確認することが重要です。
理由:積載車の手配と長距離回送
- 到着時間: ロードサービスの到着目安は、一般的に30〜90分程度の幅があります。
- 料金: 保険付帯のロードサービスを利用する場合、回送距離(レッカーで車を運ぶ距離)の無料枠が設定されています。無料回送距離を超過すると、1kmあたり超過料金が発生します。
- 夜間割増: 夜間割増は、基本料金や作業料金に1.2〜1.5倍程度の割増が適用される場合があります。
具体例:保管料の発生リスク
水没車対応では、すぐに修理に取り掛かれず、工場やロードサービスの指定する保管料が発生する場合があります。
まとめ
レッカー依頼の際は、積載車が必要な旨を伝え、回送距離と料金の概算(夜間割増、保管料含む)を必ず確認しましょう。
費用・時間の一般レンジ例
| 項目 | 一般的レンジ |
|---|---|
| 到着時間 | 30〜90分 |
| 回送超過 | 1kmあたり[例:500円〜1,000円] |
| 夜間割増 | 基本・作業の[例:1.2〜1.5倍] |
| 保管料 | 1日あたり[例:3,000円〜5,000円] |
保険・補助の考え方:車両保険の水害特約・ロードサービス付帯・自己負担の整理
ポイント一言:浸水故障は車両保険の水害特約でカバーされる場合が多い
水没車対応の修理費用は高額になることが多いため、ご自身の車両保険が水害をカバーしているかを確認することが重要です。
理由:車両保険のタイプと水害補償
- 車両保険の種類: 車両保険には、一般補償とエコノミープラン(エコノミー+A特約など)があります。
- 水害特約(一般論): 一般的に、車両保険のエコノミー+A特約でも、台風・洪水による浸水故障は補償対象となることが多いです。ただし、地震による津波は補償対象外となるのが一般的です。
- ロードサービス付帯: 任意保険に付帯しているロードサービスは、回送距離の費用をカバーしてくれることが多いため、レッカー依頼基準を超えた搬送が必要な場合に活用できます。
具体例:自己負担の整理
車両保険を使用する場合、免責金額(自己負担額)が発生します。修理費用が車両保険を使うに値するかどうか、免責金額や翌年の等級ダウン(1事故につき3等級ダウンが原則)を考慮して検討する必要性があります。
まとめ
水没車対応の費用は、ご自身の車両保険の水害特約の有無によって自己負担額が大きく変わります。
まとめ&FAQ:再発防止(通行前判断・経路計画・常備品)とQ1〜Q5
ポイント一言:浸水故障を防ぐには「通行しない勇気」が最大の対処法
冠水路での故障は、ハイドロロックという致命傷につながる危険なトラブルです。最も重要な対処法は、水深が不明な場所や、床下浸水の目安を超える水たまりには「通行しない勇気」を持つことです。
再発防止チェック
- 経路計画: 大雨警報発令時は、冠水しやすいアンダーパス(くぐり抜け道路)を避けた経路計画を立てる。
- 常備品: 反射ベストや懐中ライト、携帯電話のモバイルバッテリーなど、安全に退避し、通報するための常備品を車内に置いておく。
よくある質問(Q1〜Q5)
Q1:冠水路を抜けた後、エンジンの調子が悪くなければ走行しても大丈夫ですか?
A:再始動できてエンジンの調子が良くても、ブレーキ系統や電装系のトラブルが潜んでいる可能性があり注意が必要です。特に電装系ECUやO2センサー、オルタネーターなどは、水濡れ後、時間差でショートや断線(P0155などの故障コードを検出)が発生することがあります。AT・CVTの内部に水が浸入しているリスクもあるため、速やかに整備工場で点検を受けることを強く推奨します。
Q2:浸水した車を牽引フックで引っ張って、自力で冠水域から出しても大丈夫ですか?
A:短い距離を低速で、牽引フックを使って引っ張ることは可能ですが、床下浸水以上の水位だった場合、ハイドロロックを避けるため、エンジンを絶対にかけないことが条件です。EV・HV車は感電リスクがあるため、絶対ダメです。レッカー依頼基準としては、積載車による搬送が最も安全です。
Q3:冠水によりエンジンが停止し、電装系もショートしました。ヒューズを交換すれば動きますか?
A:電装系の故障はヒューズ交換だけで直る場合もありますが、冠水の場合は、ヒューズが飛ぶ原因がECUやワイヤーハーネスのショートである可能性が高く、安易にヒューズを交換して再始動を試みると、ECUの故障(P1603などのエンスト検出)を確定させてしまう危険性があります。再始動NGを徹底し、プロにレッカーを依頼してください。
Q4:水没車対応で車両保険を使うと、翌年の保険料は上がりますか?
A:車両保険を使用して修理を行った場合、事故として扱われ、翌年の保険料の等級は1事故につき3等級ダウンするのが原則です。しかし、水害による故障が車両保険の水害特約でカバーされるか、また保険を使うべきか(免責額や将来の保険料上昇を考慮して)は、ご自身の契約内容と修理費用を照らし合わせて検討する必要性があります。
Q5:エンジンに水が入ったかどうかの目安はありますか?
A:走行中にエンジンが急に停止した場合、吸気口から水が入ったハイドロロックの可能性が高いです。また、エンジンルームの吸気口が水没する水位(ボンネット上)に達した場合は、水が入っているものと見なすべきです。エンジンが不調(エンストやアイドリング不調)を起こしても、再始動は絶対ダメです。
携行品&再発防止チェックリスト
| 項目 | 備えるべき常備品 | 再発防止チェック |
|---|---|---|
| 安全確保 | 反射ベスト、懐中ライト | 人命最優先で退避 |
| 三角表示板、発炎筒 | 後方警戒を迅速に | |
| 連絡・待機 | モバイルバッテリー | 位置情報共有を維持 |
| 毛布、水、軽食 | 低体温対策 | |
| 車両点検 | - | 通行前判断(水深不明の冠水路は絶対ダメ) |
| - | ECUや電装系故障サイン(エンジンチェックランプ)に注意 |
安全・法令(必ず記載)
- 人命最優先。高電圧部(オレンジ配線・電池)や水没車には絶対に近づかない。
- 高速や悪天候では道路会社・警察・保険/ロードサービスの指示に従う。
- エンジン再始動NGを徹底し、ハイドロロックを防ぐ。

最短30分で駆けつけます!
車の故障・パンク・事故車のけん引など、
車のトラブルは「カーレスキュー隊24」に
お任せください。
便利なお支払い方法も充実!
-
現金OK

-
カード払いOK

-
後払い決済OK








